第18回健康講座 糖尿病、糖尿病予備軍といわれたら
糖尿病患者さんが増えています
![]() 日本人は糖尿病になりやすい?
日本人は糖尿病になりやすい?
日本人やアメリカインディアンなど、農耕民族は、もともと粗食でも耐えられるような体質にできています。それは、倹約遺伝子を持っていることによることがわかってきました。そのような民族の人たちに、食事の欧米化(特に高脂肪食)、自動車の普及による運動不足、ストレスなどが加わり、糖尿病を発症するのであろうと考えられています
![]() 糖尿病とはどんな病気なのでしょう
糖尿病とはどんな病気なのでしょう
糖尿病の定義は:”インスリン作用不足により起こる糖尿病は全身の代謝異常を来す疾患群で、慢性の高血糖を主徴とする。2型糖尿病はインスリン分泌低下を来す素因を含む複数の遺伝的素因に、過食、肥満、運動不足、ストレスなどの環境因子および加齢が加わり発症する”とされています。
これではちょっと難しいので、血糖値の調節についてまず解説します。
![]() 体に必要な糖分
体に必要な糖分
からだのすべての細胞は糖分(ブドウ糖)を栄養分として活動しています。食事として取り込んだ糖分は、血液中を流れ、全身の細胞内に取り込まれます。このときに重要なのがインスリンの働きです。すい臓から分泌されたインスリンが細胞に働いて糖分が細胞に取り込まれます。細胞内に取り込まれなかった糖分は血液中に残ります。
血糖値の調節は次のような流れで行われます。
食事をとる
→糖分が血液中に入ってくる
→すい臓がそれを感知し、インスリンを分泌する
→細胞は、インスリンの働きに反応し、血液中の糖分を取り込む
→血液中の糖分が減っていく
血液中の糖分の量、すなわち血糖値の一日の変化を次に示します。一日の中で血糖値は上がったり下がったりしています。朝は低く、食事とともに上がります。しかし、健常人ではその変化はわずかです。
![]() 血糖値の変動(非糖尿病)
血糖値の変動(非糖尿病)
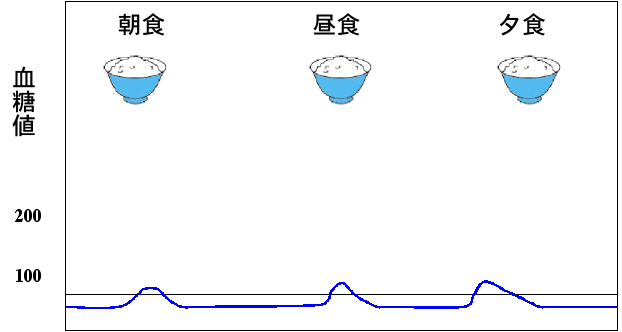
ところが、糖尿病患者さんではちょっと違ってきます。
赤の点線で示したのは軽症の糖尿病患者さんの場合の血糖値の変化です。朝はそれほど高くありませんが、食後に血糖値が上がり、下がるのにも時間がかかります。食事のたびにその変化が繰り返されます。従って、一日を平均してみると血糖値の高い時間がかなりあることになります。コントロールの悪い糖尿病患者さんでは朝から血糖値は高く、食事とともにさらに上がり、一日中血糖値が高いままです。
![]() 血糖値の変動(糖尿病患者さんの場合)
血糖値の変動(糖尿病患者さんの場合)
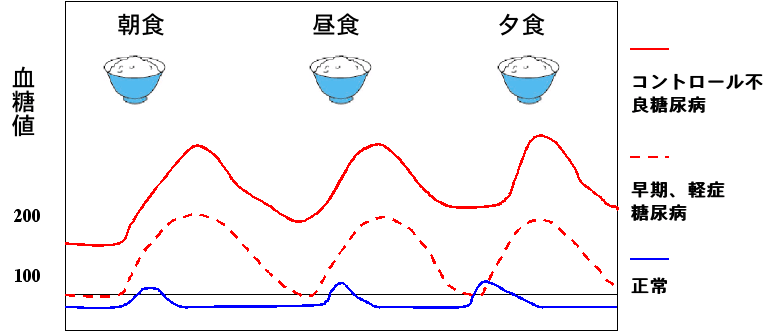
このような変化が生じるのは、糖尿病患者さんでは、すい臓からのインスリンの分泌が悪いか、あるいはインスリンが出ていても細胞がインスリンを感じないために、細胞にブドウ糖が取り込まれないという現象が起こるからです。前者をインスリン分泌不全、後者をインスリン抵抗性といいます。糖尿病患者さんでは、インスリン分泌不全やインスリン抵抗性が生じるために細胞内へのブドウ糖の取り込みが障害され、細胞の障害が起こります。そして、血液中には余ったブドウ糖が残り、高血糖として表れます。
![]() ヘモグロビンA1cとは
ヘモグロビンA1cとは
検査では血糖値だけでなく、ヘモグロビンA1cが測定されます。これは、約1〜2ヶ月間の血糖値を反映します。前述したように、軽症の糖尿病患者さんでは食前の血糖値は正常になっていることがあり、血糖値だけでは糖尿病の具合がわかりません。しかし、ヘモグロビンA1cは長期間の血糖値の平均的な状態を示してくれるので、ここ最近の血糖値が高めだったか低めだったかだわかります。正常値は5.8未満とされています。しかし、人間ドック学会などでは5.5以上あると糖尿病予備軍の可能性もあるということから5.5未満を正常値とする傾向もあります。実際、住民基本健診でもHbA1cの正常値は平成14年から5.5未満となりました。
![]() インスリン抵抗性とは
インスリン抵抗性とは
糖尿病患者さんではインスリンが出ているのに血糖値が高くなるのはどうしてでしょうか?それは、“インスリン抵抗性”といわれます。細胞(特に、筋肉、脂肪)が、インスリンの働きを受け入れにくくなっているじょうたいです。これには運動不足や脂肪の摂取量が増えていることなどが関係しているといわれています。
![]() 糖尿病の原因
糖尿病の原因
糖尿病は食べすぎるとなってしまう、一種の”ぜいたく病”のように思われがちですが、決してそれだけが下人ではなく、原因は様々な要素が重なって起こるのです。
体質についても、たとえば一卵性双生児の場合、一方の人が糖尿病でもう一人も糖尿病になる率は80%程度といわれています。つまり体質が全く同じでも発病する人としない人があるわけです。食べ過ぎや運動不足も、それだけで糖尿病になってしまうわけではありません。体質と重なって初めて発病すると考えられています。ただし、日本人の場合、前述したように糖尿病になりやすい体質を持っていますので、過食、運動不足には注意が必要でしょう。
ここでちょっとやっかいなことがあります。といのは、”糖尿病だと甘いものが食べたくなる”ということです。これはどうしてでしょう。それは次のように考えられています。
これを解消するには、まず高血糖という悪循環の最初のところを断つことが大切です。つまり、食事療法、運動療法が大切ということです。
![]() 血糖値が高いままだとどんなことが起こるのでしょう?
血糖値が高いままだとどんなことが起こるのでしょう?
糖尿病の症状と合併症
とくに、合併症のはじめの3つは糖尿病の三大合併症といわれています。
これらの合併症は、長期間(多くは10年以上)高血糖状態を続けてしまうと起こります。糖尿病のこわいところは、これらの合併症なのです。
![]() 合併症を防ぐためには
合併症を防ぐためには
![]() 血糖値を下げるためには
血糖値を下げるためには
![]() 食事療法の要点(参考文献(1)より)
食事療法の要点(参考文献(1)より)
![]() 脂肪をひかえる方法(脂肪分はカロリーも高く、特に動物性脂肪はインスリン抵抗性を増大させます)(参考文献(2)より)
脂肪をひかえる方法(脂肪分はカロリーも高く、特に動物性脂肪はインスリン抵抗性を増大させます)(参考文献(2)より)
![]() 間食はどうしてよくないか
間食はどうしてよくないか
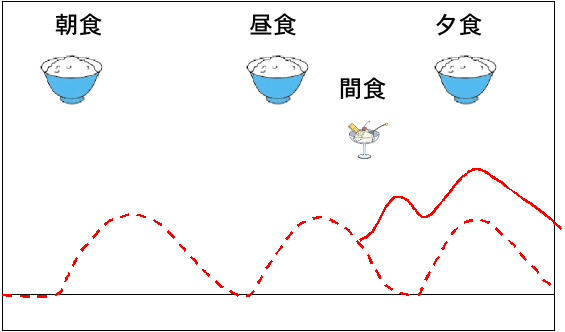
昼食後に間食をしたとします。血糖値は昼食後上昇し、徐々に下がるわけですが、間食をするとその途中でまた血糖値を上げることになります(上図、赤実線)。そして血糖値は下がりますが、間食をしなかった場合(上図、赤点線)に比べ、夕食前の血糖値は高くなります。そして夕食後再び血糖値が上がります。したがって、間食をすると、血糖値の高い時間帯が長くなり、血糖値の平均も高くなってしまうのです。
![]() 運動療法の要点
運動療法の要点
![]() 糖尿病における運動療法(参考文献(1)より)
糖尿病における運動療法(参考文献(1)より)
![]() 薬物療法
薬物療法
![]() 薬を飲むときの注意
薬を飲むときの注意
![]() 低血糖について
低血糖について
 まとめ
まとめ
<参考文献>