第24回 健康講座 脳卒中についてー予防と対策ー
 脳卒中とは、どんな病気?
脳卒中とは、どんな病気?
- 突然、脳に障害が起こる病気
- 命に関わることもある
- 麻痺などを残すこともある
- 日本人は欧米人の2-3倍多い
脳卒中というとこのように恐い病気のイメージが強いと思いますが、その原因として、生活習慣病が重要視されています。
- 高血圧、高コレステロール血症、糖尿病などの”生活習慣病”が危険因子として重要
したがって、生活習慣病の管理などが大切です。
- 危険因子を減らし、日常生活に注意をすることによって発病を防ぐことができる
 脳卒中は増えているか?
脳卒中は増えているか?
- 死亡原因としての脳卒中は減少傾向にあります。以前は死亡原因の1位でしたが、現在は、がん、心疾患に続く第3位になっています。脳卒中は大きく分けて脳梗塞と脳出血に分かれますが、最近の傾向として、脳出血は減ったものの、脳梗塞はやや増加の傾向にあります。
- 脳卒中の発症率の推移
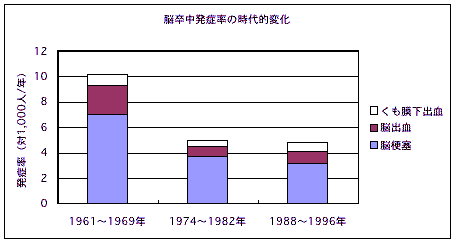
 脳卒中は寝たきりの原因の1位
脳卒中は寝たきりの原因の1位
- また、脳卒中で命は助かっても後遺症が残る場合も多く、特に、寝たきりの原因となることもあります。寝たきりになってしまう原因はいろいろありますが、脳卒中はその38.7%で一位。二位以下は骨粗鬆症13.2%、痴呆7.0%です。
 脳卒中の分類。”脳卒中”は次のように分類されます。
脳卒中の分類。”脳卒中”は次のように分類されます。
- 脳梗塞
- アテローム血栓性脳梗塞(太い血管に動脈硬化が起こり、血管が詰まるために脳のある程度の領域に障害が出ます)
- ラクナ梗塞(細い血管が詰まるため、脳のごく狭い範囲(直径15mm以下)の障害が出ます。症状がまったくない場合もあります
- 心原性脳塞栓(心臓に血栓(血のかたまり)ができて、それが脳の血管に流れて太い血管をふさいでしまうため、急速に脳の広い範囲の障害が出ます。心房細動、心臓弁膜症などの特殊な心臓病の場合に起こりえます)
- 脳出血
- 脳内出血(多くは高血圧のため、脳の中の血管が破れ、出血の周囲の脳のを障害します)
- くも膜下出血(脳の周りの動脈に動脈瘤という破れやすい部分ができて、あるときそれが破れて出血し、脳を圧迫します)
 脳卒中の症状
脳卒中の症状
- 以下のような症状の違いはありますが、いずれもならずにすませたいものです。いずれも予防は共通します。
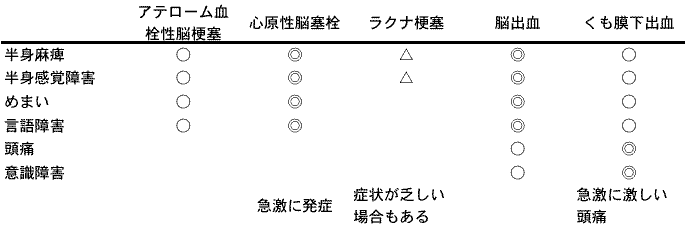

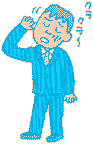
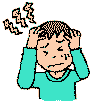
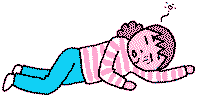
脳卒中の後遺症
- 脳の細胞が再生しなければ麻痺などの症状が残る
- 脳の細胞が再生すれば回復の可能性あり→早期に治療を開始する必要
- 脳内の他の細胞が代用→リハビリの重要性
 どうして麻痺が起こるのか
どうして麻痺が起こるのか
- 脳梗塞:脳血管が詰まり、脳細胞に血液が行かなくなり、脳細胞が栄養障害になり、壊死におちいる
- 脳出血:脳内で出血が起こり、脳の細胞が圧迫され脳細胞が壊死に陥る
脳の構造としくみ
- 脳には140億個の細胞があり、それぞれが決められた役割を持っています。そして、たとえば、右手を動かすための細胞の集まり、右足を動かすための細胞の集まりなどの領域は脳の中のどこの領域、ということも決まっています。そして、それらの領域に血液を供給する血管もまた決まっています。ですから、ある血管が詰まるとその領域の脳の働きが障害されてしまいます。たとえば、細い血管が詰まった場合、たとえば、右足の動きが障害されるということが決まってしまいます。もし太い血管が詰まれば広い範囲の脳に障害が残り、それだけ多くの障害が出ることになります。
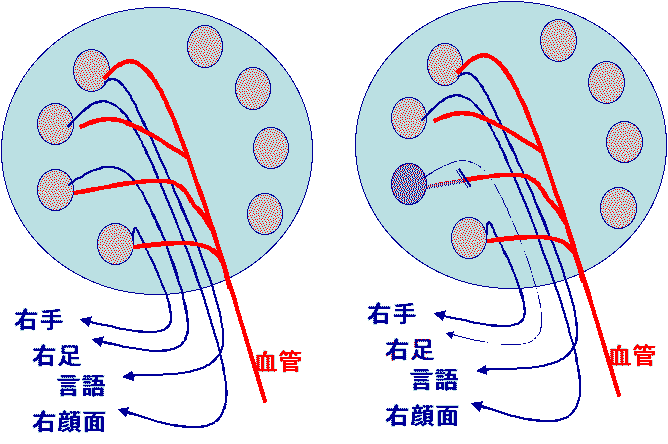
 脳卒中の前触れ
脳卒中の前触れ
そのような脳卒中も、突然起こる場合ばかりでなく、特に脳梗塞では前触れともいえる症状があらわれることがあります。たとえば次のような症状です。
- 急に物を持てなくなる、物を落とす
- 片側の手足のしびれ
- 言葉がうまく出ない、ろれつが回らない
- 物が二重に見える
- めまいがしたりふらついたりする
- 一方の目が見えなくなる。視野が欠ける
- 呼びかけに対する反応が鈍い
このようのな前触れ症状は、一過性脳虚血発作と呼ばれ、脳梗塞になる危険性が高く、予防的治療が必要です。気になったらすぐに受診しましょう。
 一過性脳虚血発作
一過性脳虚血発作
- 脳の血管が詰まりかかったときにおこる
- 数分間から数時間以内、長くても24時間以内に症状は消失
- 脳梗塞(特にアテローム血栓性脳梗塞)の前兆として重要
では、脳梗塞の原因は何でしょう。次のようなことが考えられています。
 脳卒中の原因
脳卒中の原因
- 動脈硬化
- 血管が狭くなる→血管が詰まる
- 血管が硬く、もろくなる→血管が破れる
- 心臓内に血液のかたまりができる(不整脈、特に心房細動、弁膜症など)→血液のかたまりが脳の血管に流れ、血管をふさぐ
- 脳血管に動脈瘤ができそれが破れる
- =くも膜下出血
したがって、動脈硬化の予防が大切ということになります
また、脳梗塞の危険因子として次のようなこともいわれています。
 危険因子ーこんな人がなりやすいー
危険因子ーこんな人がなりやすいー
- 高血圧
- 心臓病
- 糖尿病
- 喫煙
- 高脂血症
- 高尿酸症
- 飲酒(飲み過ぎ)
- 運動不足、肥満
- 遺伝=“体質”
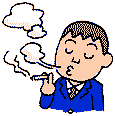

危険因子の変遷
最近の傾向として、高血圧の人は減っていますが、高コレステロール血症、糖尿病、肥満はむしろ増えています。今後も脳梗塞の予防が大切になってきます。
ー脳卒中の予防のためにー
どんなときに脳卒中は起きるのか
- 入浴中や用便中
- 気温の変動
- 運動・労作
- 精神的興奮などによる血圧の急激な変動
以上のような状況で脳卒中は起きやすいといわれていますのでその対策についても後述します。
 脳卒中の予防
脳卒中の予防 のポイント
のポイント
- 高血圧の治療を
- 心臓病(心房細動、弁膜症)の治療
- 糖尿病、高脂血症、高尿酸血症の治療
- 肥満の解消
- 急激な温度差に注意、入浴、夜間のトイレなど要注意
- 食生活
- ストレス
- 運動不足に注意
- 脱水に注意
- 禁煙
- アルコールは控えめに
個々のポイントについて解説します
(1)肥満の解消
- 腹七〜八分目
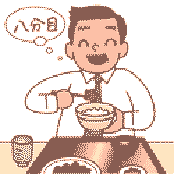
- 間食を控えましょう
- 油を使った料理を控えめに
- 適度な運動を
 (2)入浴の工夫
(2)入浴の工夫
- 浴室を暖かくしておく
- 湯の温度は冬なら40℃、夏なら38℃くらいのぬるめがよい
- 肩までつかってゆっくり入る
- 浅い風呂で身体をかがめて入るのはよくない=腹圧がかかり血圧が上がるため
- 入浴剤も使ってリラックス
(3)寒さに注意
- 暖かい部屋から急に寒い外へ出るときは要注意
- 暖かい服装にしてから外へ出るように
- 入浴時、脱衣場の温度に注意
- 夜間、早朝のトイレにも注意
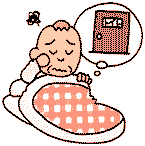 (4)夜間のトイレなど
(4)夜間のトイレなど
- 家の中の温度が平均的になるように
- トイレにも暖房を
- 就寝後のトイレに備えてガウンなどを寝床のそばに置いておく
- 特に布団で寝ているときは夜中、明け方の冷気に注意
(5)食生活
- 塩分を控える
- 新鮮な素材を、季節の食材を選ぶ
- おいしいだしをとる
- 表面に味付けをする
- 香りや風味を生かす
- 酢、酸味、香辛料を利用
- 焼き味、焦げ味を付ける
- 脂肪を控える
- 食物繊維を多くとる
(6)ストレス
- ストレスによって、血圧上昇、心拍数増加、不整脈などの原因になる
- 気分転換の方法を見つけておく
- 睡眠不足が続かないように
(7)便秘にならないように
- 便秘をすると排便時に力んで血圧が上がる
- 食物繊維を多くとる
- 朝起きたらコップ1杯の水を飲む
- 頑固な便秘には薬を
(8)運動
- 1日20〜30分のウォーキング、水泳などの有酸素運動はよい
- 冬の寒さの中での運動は控える
- 夏の運動時には水分補給を忘れずに
- スポーツ時の水分補給に塩分は必要ない
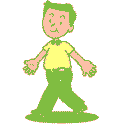
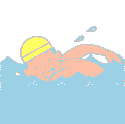
(9)脱水にならないように
- 夏の運動時、外出時は水分をこまめに補給を
- 朝起きたらコップ1杯の水を飲みましょう
- 血液粘度の上昇は午前中に起こることが多く、猛暑下の脳梗塞の発症も午前中が多い
- 起床後に十分な水分をとることが重要
- 気温、湿度の高い日の、外での運動や労働を避ける
- 補う水分量の目安(野球などのスポーツの場合)
- 運動前に250〜500ml
- 1時間ごとに500〜1000ml
- 温度、運動量により調節
(10)アルコールと脳卒中
- 脳出血は飲酒量が多いほど発症率が高い
- 脳梗塞は1.5合以上の飲酒で発症率が高くなる
- 日本酒なら1合、ビールなら大ビン1本まで
- 週に何回かは飲まない日を作る
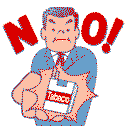 (11)禁煙を
(11)禁煙を
- 1日20本タバコを吸う人が、脳卒中になったときの死亡率は、タバコを吸わない人の2倍以上高い
- タバコをやめると、脳梗塞になる危険率は2〜3年でタバコを吸わない人と同じになる
(12) 薬について
薬について
- 高血圧、高コレステロール血症、糖尿病などの薬は医師の指示に従い続けましょう
- 不整脈の薬、血液を固まりにくくする薬などが処方されている場合も続けましょう
 万が一の場合・・・
万が一の場合・・・
脳卒中で倒れた人がいたら(脳卒中かどうかわからない場合がほとんどですが、突然意識を失って倒れたような場合)
- 安静に寝かせる
- 頭は高くしない
- 顔は横を向ける(嘔吐する場合に備えて)
- 救急車をすぐに呼ぶ
- 119番→”救急ですか、消防ですか?” →救急です
- 年齢、性別、どんな症状か持病はあるか、意識の状態は(呼びかけに答えるか)、手足の動きは、などを簡潔に説明
 まとめ
まとめ
- 脳梗塞の予防は、生活習慣病の予防、管理が大切です
- 生活習慣病の予防・治療のための、食事療法、運動療法などを続けましょう
- 気温の変化に注意し、家の中でも室温の変化が少なくなるように工夫しましょう
- 水分補給をこまめにしましょう
- アルコールはほどほどに、タバコはやめましょう
- 予防のための薬はきちんと続けましょう
<参考文献>
- 生活習慣病を防ぐー健康寿命をめざしてー 香川靖雄著、岩波新書
- 高脂血症ー手当てしないと心筋梗塞・脳梗塞になるー 菅原正弘著 講談社健康ライブラリー
- 新訂もう脳卒中なんかこわくないー予防から最新治療法までー作田学著 みずうみ書房
- 脳梗塞がよくわかる本 岩田誠著 小学館
- 心臓が悪い人の食事 太田昭夫、住田佳寿子著、保健同人社
![]() 脳卒中とは、どんな病気?
脳卒中とは、どんな病気?![]() 脳卒中は増えているか?
脳卒中は増えているか?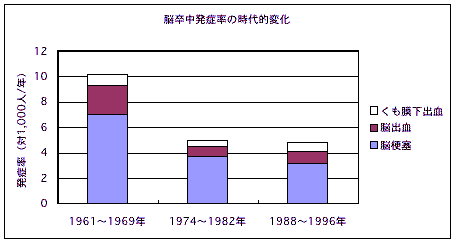
![]() 脳卒中は寝たきりの原因の1位
脳卒中は寝たきりの原因の1位![]() 脳卒中の分類。”脳卒中”は次のように分類されます。
脳卒中の分類。”脳卒中”は次のように分類されます。![]() 脳卒中の症状
脳卒中の症状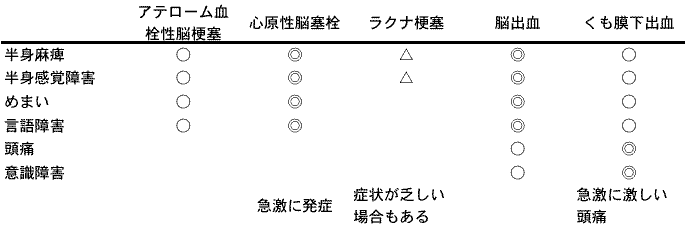

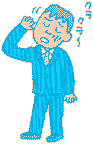
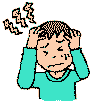
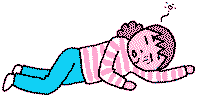
![]() どうして麻痺が起こるのか
どうして麻痺が起こるのか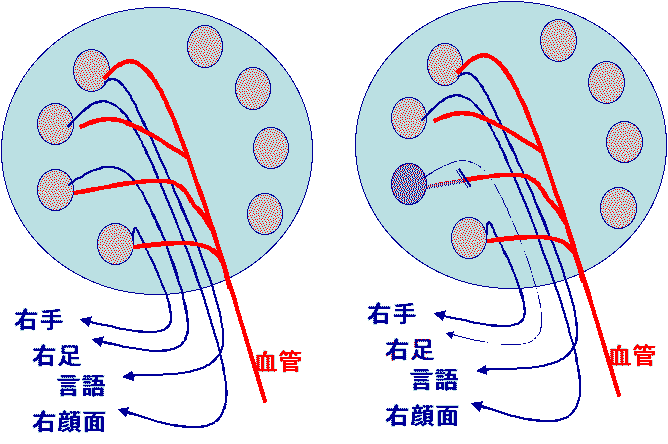
![]() 脳卒中の前触れ
脳卒中の前触れ![]() 一過性脳虚血発作
一過性脳虚血発作![]() 脳卒中の原因
脳卒中の原因![]() 危険因子ーこんな人がなりやすいー
危険因子ーこんな人がなりやすいー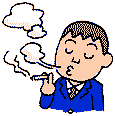

![]()
![]() 脳卒中の予防
脳卒中の予防 のポイント
のポイント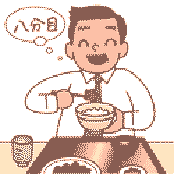
![]() (2)入浴の工夫
(2)入浴の工夫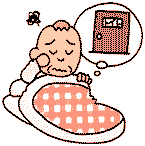 (4)夜間のトイレなど
(4)夜間のトイレなど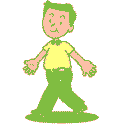
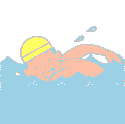
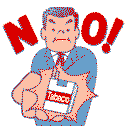 (11)禁煙を
(11)禁煙を 薬について
薬について![]() 万が一の場合・・・
万が一の場合・・・![]()
![]() まとめ
まとめ