第27回健康講座 高血圧を克服するために
今回は、高血圧の治療のために皆さんに知っておいていただきたいことをご紹介させていただきたいと思います。特に、昨年末に高血圧治療ガイドラインが改定され、生活習慣の見直しに対して、より力を入れた治療が勧められています。その点も踏まえ、今日は以下のような内容でお話しを進めたいと思います。
- 高血圧の原因と合併症について
- 高血圧の治療のために
- 生活習慣について
- 生活習慣改善の効果
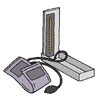
 高血圧の原因
高血圧の原因
- 高血圧の原因は一つではなく、遺伝的な体質と様々な環境因子が重なって発症すると考えられています。環境因子としては加齢、塩分のとりすぎ、肥満、過度の飲酒、喫煙、寒冷、ストレスなどが挙げられます。
 高血圧はなぜ治療が必要か
高血圧はなぜ治療が必要か
- 高血圧の怖いところは、無症状のまま進み、様々な合併症を起こすことです。合併症には脳血管障害(脳出血、脳梗塞、くも膜下出血、一過性脳虚血発作など)、心疾患(心肥大、狭心症、心筋梗塞、不整脈、心不全など)、腎機能障害(腎不全、たんぱく尿など)、眼底出血、動脈硬化(主要臓器血流障害、四肢血流障害、動脈瘤など)が挙げられます(参考文献4)。それらの合併症を予防することこそが高血圧の治療の目標です。
実際、高血圧を治療するとどの程度の予防効果があるかというと、高血圧を薬で治療することにより脳卒中は5年間で39%減少、心筋梗塞は16%減少した、という欧米の大規模臨床試験のデータがあります。また、日本人についても、ここ20〜30年間に日本人の血圧は低下し、脳卒中による死亡率も1/4以下まで減少したというデータもあります。すなわち、血圧を下げるようにすればそれらの合併症を予防することができることが証明されたといえます。
しかし、それではまだ予防効果として不十分ともいえます。不十分な理由としては、
- 降圧(血圧を下げること)の程度が不十分
- 原因をなおしていないから
などが考えられており、そのためには生活習慣も改善し、原因治療と、さらなる降圧を得ることが重要と考えられます(参考文献1より)。
 高血圧治療のために必要な生活習慣の見直し
高血圧治療のために必要な生活習慣の見直し
 高血圧の治療のためには次のような生活習慣の見直しが大切です(参考文献3より)。
高血圧の治療のためには次のような生活習慣の見直しが大切です(参考文献3より)。
- 食塩制限 6g/日未満
- 野菜や果物の積極的摂取
- コレステロールや飽和脂肪酸の摂取を控える
- 適正体重の維持(BMIで25を超えない)
- 運動療法:心血管病のない人が対象、有酸素運動を毎日30分以上を目標に
- アルコール制限
- 禁煙
 日本人の食塩摂取量について
日本人の食塩摂取量について
- 日本人の平均塩分摂取量は徐々に減っていますが、まだ多いのが現状です。2002年時点で平均11.4gとなっています。
 減塩の効果
減塩の効果
- 無塩食にすると2〜3週間で血圧が下がってくることが知られています。実際に無塩食にすることは困難ですが、1日6gに減塩することで3mmHg下がるといわれています(参考文献1、2より)のでそれを目標に減塩に取り組んでみましょう。
- 最近の欧米の大規模臨床試験でも、1日8.5gの塩分摂取量を6.1gに減らしたところ降圧効果を認め、副作用も見られなかったという報告があります。また、減塩指導を高校生に試みて降圧に成功し、将来の高血圧予防のために、幼・若年者に対して減塩を勧めるべきという指摘もあります(参考文献3より)。
では、実際に減塩する上でどんな工夫をしたらよいでしょう。
 減塩のコツ(参考文献2より)
減塩のコツ(参考文献2より)
減塩するとかえって塩あじを楽しむことができ、おいしく食事ができます。食品素材の風味を生かし、温かい料理にしましょう。食酢、花鰹、香辛料をうまく使ってください。香辛料では血圧は上がりません。具体的には下の1〜7に気をつけましょう。
- インスタント食品やかまぼこ、ちくわ、ハム、ソーセージ、ベーコンなどの加工保存食品を控える
- 麺類の汁は残す
- すき焼きをみずたき、しゃぶしゃぶに変える
- 寿司飯、味付けご飯、どんぶりを控える
- スープ、味噌汁は薄味にする
- 味のついているものに食卓塩をかけない
- 漬け物を減らす。古漬けより浅漬けにする
 おいしい薄味を演出するために次のようなことがよいといわれています(参考文献5より)
おいしい薄味を演出するために次のようなことがよいといわれています(参考文献5より)
- 新鮮な材料を使う
- 香りや風味、香辛料を利用する
- 味は仕上がり際に整える
- 酢を利用する
- 海草やきのこのうまみを活用する
- 加工食品はあまり使わない
- 減塩しょうゆで塩分のセルフサービスを
 減塩のために知っておきたいこと(参考文献5より)
減塩のために知っておきたいこと(参考文献5より)
- 食塩1gは小さじ1/5杯
- しょうゆ小さじ1杯
- 減塩しょうゆ小さじ2杯
- 味噌大さじ1/2杯弱
- ソース小さじ2杯
- 洋風スープのもと1個に2〜3gの塩分
- 顆粒状の和風だし小さじ一杯で1.5gの塩分
 |
 |
| 塩1gはこのくらいです。意外と多いですね。 |
塩1gに相当する醤油はこのくらいです。お刺身などを食べるとこのくらいすぐ使ってしまいませんか? |
 |
 |
| 塩4gに相当するみそはこのくらいです。みそ汁2杯分。つまり、みそ汁1杯で塩2gです。 |
とんかつソース17mlで塩1gです。とんかつを食べるときこのくらいはかけてしまいませんか。 |
塩分のとりすぎの原因は、塩そのものよりも調味料や漬け物、加工食品からとりすぎていることが多いだろうと思います。
 栄養表示につい
栄養表示につい
て
 塩分以外に大切なポイントとして次のようなことがあげられます(参考文献2より)
塩分以外に大切なポイントとして次のようなことがあげられます(参考文献2より)
- 肥満の人が体重を3kg減らすと血圧が高くない人では2mmHg、高めの人では5mmHg程度下がる
- 毎日2合の日本酒を飲んでいる人が1合減らすと軽症高血圧の人では5mmHg低下する
- カリウムを多くとると6mmHg程度下がる
 カリウムをとることの意味
カリウムをとることの意味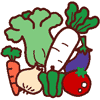
- カリウムは腎臓でナトリウムと交換されて尿中に排泄されます
- カリウムを多くとると排泄されるナトリウムが増えます
- 野菜、果物にカリウムは多く含まれています
 カルシウム、マグネシウムも大事
カルシウム、マグネシウムも大事
 コレステロール、飽和脂肪酸を控えましょう
コレステロール、飽和脂肪酸を控えましょう
- コレステロールや飽和脂肪酸は内臓脂肪を増やし、高血圧の合併症も増やすことにつながります
- コレステロールは、卵類(鶏卵、魚卵)、肉類、ウナギなどに多く含まれます
- 飽和脂肪酸とは、動物性の脂肪のことで、肉の脂身、バター、ラードなどに含まれます
- 逆に、不飽和脂肪酸は、植物油で、サラダオイル、オリーブオイル、ごま油などです
- 不飽和脂肪酸は動脈硬化を防ぐ働きがあります
 食物繊維
食物繊維
- コレステロールや塩分の吸収を抑えます
- 低カロリーなので減量に役立ちます
- きのこ、海草類、こんにゃくなどが食物繊維豊富です


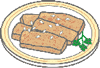
 ”DASH食”について
”DASH食”について
- 高血圧対策として考案された食事で、次のような特徴があります
- 飽和脂肪酸とコレステロールが少なく、カルシウムが多い
- カリウム、マグネシウム、食物繊維が多い
- 低脂肪乳製品、野菜、果物多い
- この食事療法により、中等度の高血圧患者で11.4/5.5mmHgの降圧効果が得られたという報告があります
 平均的日本人の食事と”DASH食”との比較
平均的日本人の食事と”DASH食”との比較
- 平均的日本人の食事に比べ、塩分が少なく、不飽和脂肪酸が多く、コレステロールが少なく、食物繊維、カリウム、カルシウム、マグネシウムが多いことが特徴です
- そのためには、塩分は控えながら、伝統的な日本食にたちかえり(野菜が多く、肉類は少ない)、コレステロールの多い卵などは控え、低脂肪乳製品を補うのがよいと考えられます
 アルコールについて
アルコールについて
- 日本酒にして一合程度の飲酒は、節酒により1〜2週間で5mmHgより大きく低下するといわれています
- エタノール量では
- 男性:20〜30ml/日以下
- 女性:10〜20ml/日以下

- ビール:400ml
- ワイン:153ml
- 焼酎:80ml
- 酎ハイ:285ml
- ウィスキー:46ml
- 日本酒にして一合程度の飲酒は、節酒により1〜2週間で5mmHgより大きく低下(参考文献2より)
 禁煙は重要
禁煙は重要
- 喫煙により動脈硬化が進みやすくなります
- 高血圧の合併症が起こりやすくなります
- タバコをやめて1-2年で脳卒中、心臓病に対する危険性はなくなると考えられています
- 禁煙を助けるための補助薬もあります
 運動のポイント(参考文献1より)
運動のポイント(参考文献1より)
- ”ニコニコペース”の運動(一日30分間)で血圧は11/6mmHg下がる
- 軽い運動では運動中の血圧は上がりませんが、激しい運動になると50以上上がりますから、運動強度には注意が必要です
- 息が上がるような競技スポーツではなく、多少、呼吸や脈が速くなっても、隣の人と話ながらニコニコしながら続けられる程度の運動強度で続けるのがよいとされています
 寒冷対策
寒冷対策
- 冬は血圧が上がりやすくなります
- 暖房、防寒に注意しましょう
- トイレ、浴室の暖房を上手に使いましょう
 入浴に関して
入浴に関して
- 熱すぎない風呂がよいとされています
- 室温20℃以上、湯温40℃以下では血圧はほとんど上昇しないといわれています
- 38〜42℃くらいで5〜10分間の入浴がよいでしょう
 生活習慣修正による降圧の程度
生活習慣修正による降圧の程度
- 血圧を下げる効果のある生活習慣改善策は減塩ばかりではありません(参考文献3より)
- 生活習慣修正による高圧程度をまとめると次のようになります
- 減塩により5mmHg前後
- DASH食により11mmHg前後
- 10kgの減量により 11mmHg前後
- 運動により 8mmHg前後
- 節酒により 4mmHg前後
 血圧低下の期待値(参考文献2より)
血圧低下の期待値(参考文献2より)
| BMI減少分*x2mmHg |
mmHg |
| 減塩 (g)**x0.5mHg |
mmHg |
| カリウムの増加 |
2 mmHg |
| 早歩き30分 |
5- 10 mmHg |
| 合計 |
( )mmHg |
- (*たとえば、身長150cm、体重55kg(BMI 24.4)の人が体重52.6kgになるとBMIは23.4になり、BMIが1下がったことになります)
- (**1日の塩分摂取量減少分1gあたり0.5mmHg低下という意味ですので、1日の塩分を12gから8gに減らした場合は2mmHgの血圧低下が見込まれるという意味)
- つまり、減量してBMIを1減らし、塩分を4g減らし、カリウムをとるようにし、運動をすると合計で11〜16mmHgの血圧低下が見込まれるということになります。これは薬よりも効果があるとも言えます。
<まとめ>
高血圧の治療には薬以外に次のような大切なポイントがあり、うまく組み合わせて行えば薬以上の効果も見込まれます
- 食塩制限 6g/日未満
- 野菜や果物の積極的摂取
- コレステロールや飽和脂肪酸の摂取を控える
- 適正体重の維持(BMIで25を超えない)
- 運動療法:心血管病のない人が対象、有酸素運動を毎日30分以上を目標に
- アルコール制限
- 禁煙
<参考文献>
- 荒川規矩男:薬を使わずに血圧を下げる、高血圧の予防と管理 、p1-27、日本高血圧学会監修、学会センター関西2001年
- 上島弘嗣:生活習慣の改善で高血圧を予防する、高血圧の予防と管理 、p29-52、日本高血圧学会監修、学会センター関西2001年
- 高血圧治療ガイドライン2004、日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編
- 塩之入洋:高血圧の医学 あなたの薬と自己管理、中公新書
- 太田昭夫、住田佳寿子、心臓が悪い人の食事、保険同人社
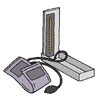
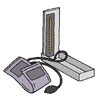
![]() 高血圧の原因
高血圧の原因![]() 高血圧はなぜ治療が必要か
高血圧はなぜ治療が必要か![]() 高血圧治療のために必要な生活習慣の見直し
高血圧治療のために必要な生活習慣の見直し![]() 高血圧の治療のためには次のような生活習慣の見直しが大切です(参考文献3より)。
高血圧の治療のためには次のような生活習慣の見直しが大切です(参考文献3より)。![]() 日本人の食塩摂取量について
日本人の食塩摂取量について![]() 減塩の効果
減塩の効果![]() 減塩のコツ(参考文献2より)
減塩のコツ(参考文献2より)![]() おいしい薄味を演出するために次のようなことがよいといわれています(参考文献5より)
おいしい薄味を演出するために次のようなことがよいといわれています(参考文献5より)![]() 減塩のために知っておきたいこと(参考文献5より)
減塩のために知っておきたいこと(参考文献5より)![]() 栄養表示につい
栄養表示につい![]() 塩分以外に大切なポイントとして次のようなことがあげられます(参考文献2より)
塩分以外に大切なポイントとして次のようなことがあげられます(参考文献2より)![]() カリウムをとることの意味
カリウムをとることの意味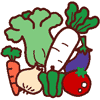
![]() カルシウム、マグネシウムも大事
カルシウム、マグネシウムも大事![]() コレステロール、飽和脂肪酸を控えましょう
コレステロール、飽和脂肪酸を控えましょう![]() 食物繊維
食物繊維

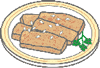
![]() ”DASH食”について
”DASH食”について![]() 平均的日本人の食事と”DASH食”との比較
平均的日本人の食事と”DASH食”との比較![]() アルコールについて
アルコールについて
![]() 禁煙は重要
禁煙は重要![]() 運動のポイント(参考文献1より)
運動のポイント(参考文献1より)![]() 寒冷対策
寒冷対策![]() 入浴に関して
入浴に関して![]() 生活習慣修正による降圧の程度
生活習慣修正による降圧の程度![]() 血圧低下の期待値(参考文献2より)
血圧低下の期待値(参考文献2より)![]()
![]()