第30回健康講座 インフルエンザについて
平成17年12月12日(月)、14日(水)
<本日の予定>
- インフルエンザとは
- 症状、合併症
- インフルエンザの予防
- インフルエンザの治療
- 新型インフルエンザについて
|
 インフルエンザの特徴
インフルエンザの特徴
- 普通の”かぜ”とはちょっと違います
- 普通の”かぜ”より感染力も強く、症状も重いことが特徴です
- インフルエンザウイルスが感染することによって起こる感染症です
- つまり、ヒトからヒトへうつっていく(感染する)病気です
- 突然の発熱で始まることが多く、普通の風邪よりも症状は重い
- 毎年冬に流行
- 年によっては大流行する
- 高齢者では肺炎を併発し、重症化することも多い
 インフルエンザの症状
インフルエンザの症状
- 潜伏期間1〜2日
- 家族の中の誰かがかかると1〜2日後に別の家族が発病する、ということがよくあります
- 発熱、全身倦怠感、食欲低下、筋肉痛、関節痛などの全身症状があります
- くしゃみ、鼻水、咳、痰など呼吸器症状があります
- 顔面紅潮、結膜充血なども認めることがあります
- 合併症がなければ、5日くらいで軽快に向かいます
- 合併症があると治るまでに時間がかかります
- 肺炎、脳炎を合併することもあります
- 特に、高齢者では肺炎、小児では脳炎の合併に注意が必要です
 インフルエンザの合併症
インフルエンザの合併症
- 肺炎:
- 成人のインフルエンザの3〜25%に肺炎を合併するといわれています
- 高齢者では重篤になりやすい特徴があります
- したがって、予防が重要です
- 脳炎:
- 主に小児の合併症です
- 非常にまれですが、重篤な後遺症を残したり、致命的になる場合もあります
- 解熱剤との関連も指摘されています
 年齢別罹病率と死亡率
年齢別罹病率と死亡率
- 罹病率(かかりやすさ)は小児に多いが、死亡率は高齢者ほど高いことがわかっています
そのようなインフルエンザを予防する方法について考えていきましょう
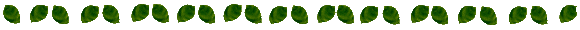
 インフルエンザの予防には次のようなものが挙げられます
インフルエンザの予防には次のようなものが挙げられます
 予防接種
予防接種
- 平成13年より65歳以上には公費負担の制度ができました。任意接種です(ご本人の希望で)。
- 65歳以下の人は受けなくてもよい、という意味ではありません。できるだけ多くに人に受けていただきたいものです。
- ワクチンの効果1:発病予防の効果
- 65歳以下の成人での発病予防有効率80%といわれています
- 予防接種を受けずに発病した人たちがもし受けていれば80%の人が発病せずにすんだという意味
- ワクチンの効果2:高齢者の入院を減らす効果
- 高齢者の入院を減らす効果は50%とされています
- 予防接種を受けずにインフルエンザになって入院することになった人が1000人いたとすると、その人達が予防接種を受けていれば500人は入院しなくてすんだ、と考えられます
- ワクチンの効果3:高齢者の合併症による死亡を減らす効果
- 高齢者の合併症による死亡を減らす効果は、アメリカ、日本とも80%とされています
このようにワクチンには、発病を防ぎ、重症化を防ぐ効果があると考えられます。
 学童へのインフルエンザ予防接種の効果
学童へのインフルエンザ予防接種の効果
- 平成6年までは学童には集団接種が行われていました
- インフルエンザの流行は学校で始まることから、学童の感染を抑えれば国民全体の感染を減らせるだろう、という考えから行われていましたが、それ以来任意接種となっています。
- 振り返って調べてみると、平成6年以降、高齢者の超過死亡が増えており、学童へのインフルエンザ予防の効果はあったのではないか、と考えられていいます。
 脳炎・脳症の合併予防効果
脳炎・脳症の合併予防効果
- 1999年1月から3月のインフルエンザシーズンに厚生省が全国集計した、インフルエンザの臨床経過中に認められた脳炎・脳症の症例は、0歳から60歳までで217例。
- このうちインフルエンザワクチンを受けていた人は一人もいなかったとされています。
インフルエンザ予防接種はいつ頃うつのがよいでしょうか?
 ワクチンの接種時期
ワクチンの接種時期
- ワクチンの効果が出るのは2週間後から
- ワクチンの効果は3〜6ヶ月間持続
- インフルエンザの流行は1月〜4月
- ワクチンは11月中、遅くても年内にうっておくのがよい
 ワクチンの効果をまとめますと次のようになります
ワクチンの効果をまとめますと次のようになります
- 発病予防効果は100%ではないが、十分な効果がある
- 肺炎、脳炎などの合併症を予防する効果もある
- 接種は11月から12月中旬がよい。
そんな効果の高いワクチンですが、薬である以上多少の副作用はあります。ワクチンの場合は”副反応”といいます。
 ワクチンの副反応
ワクチンの副反応
- 接種局所の発赤、疼痛、発熱などの全身症状が起こることがあります
- 約11%の人に起こるといわれています
- 多くは2〜3日で自然に軽快します
- 卵による重症なアレルギー反応を起こす人は接種を控えた方がよい、とされています

予防接種以外の予防法には次のようなものがあります
 一般的予防
一般的予防
 うがい
うがい
- ウイルスに対しては15〜30倍にうすめたヨードうがい液で10秒間、6回以上うがいすることでウイルスが減る、とされています
- 最近、水道水のうがいでも十分効果があることがわかってきました
- 学童のデータでは、うがいを行ったクラスではインフルエンザ罹患率も低く、欠席日数も少なかった、というものもあります
 手洗い
手洗い
- インフルエンザは飛沫感染によって感染が広まります
- ウイルスを含んだ飛沫の付着した物は多くの場所に存在します
- くしゃみや咳をしたときにだ液が手について、その手でいろいろなところを触ると、それを触れた人の手にウイルスが付着します。それを洗うことによって感染予防効果が期待できます。
- ”手洗いとうがいをセットにする!”を実行しましょう
 マスク
マスク
- インフルエンザウイルスは小さな粒子であるために、ウイルスそのものはマスクも通過してしまいます。残念ながら今のところ、インフルエンザの予防効果を示す科学的データはありませんが、くしゃみ、咳による大きい飛沫を吸い込まない効果はあります。
- ウイルスは飛沫に混入して飛散するのでそれを吸い込まないようにすることは重要です。
- また、自分が感染しているとき、他人に感染させない効果もあります。
また、、次のようなことも重要です
 一般的予防 〜日常生活〜
一般的予防 〜日常生活〜
- 体力の維持、生活の摂生
- 栄養維持、睡眠を十分に
- 感染者の多い場所への出入りを避ける、つまり、通勤電車、人混みを避けることも大事です
- どうしても出かけなければならないときはマスクを忘れずに
- 室内の環境
- 湿度を高くする
- インフルエンザウイルスは、低温、乾燥に強いウイルスです。
- 空気を入れ換える

これらの予防をしていても、インフルエンザにかかってしまうこともあるかもしれません。
 インフルエンザにかかってしまったら
インフルエンザにかかってしまったら
- 安静、睡眠を十分にとりましょう
- 水分、栄養の補給を
- 食欲が落ちて、食事が進まなくても、水分はとりましょう
- 早期治療(有効な薬あり)
- 他者への感染を避けることも大事です
 早期診断の重要性
早期診断の重要性
- 発病後48時間以内であれば有効な抗ウイルス薬が使われるようになりました
- 合併症の予防は早期治療が大切です
- 予防接種をしていてもかかることもあることは忘れずに
- 予防接種を受けたんだから、インフルエンザじゃない、と考えずに、それらしい症状があったら早めに受診を。
 インフルエンザの薬物治療
インフルエンザの薬物治療
- 発病初期
- 合併症があれば
- 病状によっては入院も必要となります

 新型インフルエンザについて
新型インフルエンザについて
今話題となっている、新型インフルエンザについて解説します。まず、ちょっと混乱しやすくなっている用語について説明します。今、インフルエンザには3種類が話題となっています。それは次の3つです。
- 普通のインフルエンザ
- 毎年流行する、ヒトからヒトへ感染するインフルエンザのことです
- トリインフルエンザ
- トリの間で広まっているインフルエンザ
- 高病原性といわれています
- ヒトへの感染はまれです
- 新型インフルエンザ
- トリインフルエンザの性質を持ち、ヒトからヒトへ感染するように変化したインフルエンザウイルスになるだろうといわれています
- 今のところまだ出現していませんが、出現は時間の問題とさえいわれています
 トリインフルエンザについて
トリインフルエンザについて
 数年前までの状況
数年前までの状況
- トリからヒトへの感染はありませんでした
- ヒトの細胞内ではウイルスが増殖しなかったからです
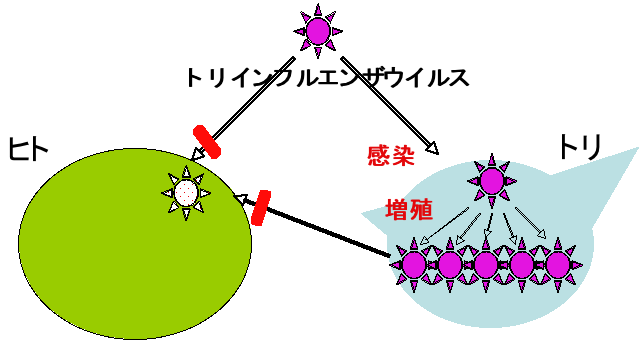
 現在の状況
現在の状況
- トリからヒトへの感染が起き始めました
- ウイルスが、ヒトの細胞内には入り込む性質を持つようになったと考えられます
- しかし、感染したヒトから他のヒトへの感染は起きていません
- トリから一度に大量のウイルスが侵入すると発病するのではないか、と考えられています
- 鶏肉を食べて感染するようなことはありません
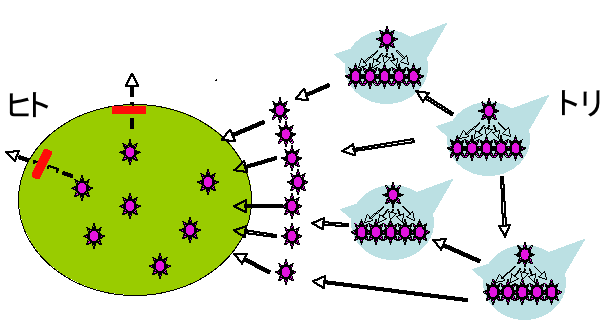
 これから起こると予想されている状況
これから起こると予想されている状況
- ヒトからヒトへの感染
- トリインフルエンザウイルスが変異し、ヒトの細胞に入り込み、ヒトの細胞内で増殖するようになるのではないかと考えられています
- ヒトからヒトへの感染が起こるようになります
- 新型インフルエンザの大流行になる、と考えられています
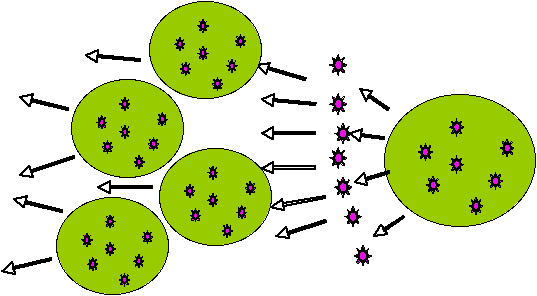
実は、このような新型インフルエンザは過去にも出現し、流行した歴史があります。今まで、10年〜30年の周期で新型インフルエンザが発生しています。
 新型インフルエンザの流行の歴史
新型インフルエンザの流行の歴史
- 1918〜1919年のスペインかぜ
- 全世界で6億人(人口20億人)が罹患、死者3000万人。我が国でも388,727人が死亡。
- 1947年イタリアかぜ。
- 1957年のアジアかぜ
- 中国南部から始まる。我が国でも98万人が罹患、7700人が死亡(人口9100万人)。
- 1968年の香港かぜ。
- 1977年ソ連かぜ。
最近の研究で、スペインかぜのウイルスは、トリインフルエンザウイルスがヒトに感染するように変異したものと考えられ、また、病原性も非常に高かったことがわかってきました。また、そのほかの過去の新型インフルエンザウイルスはトリインフルエンザウイルスとヒトインフルエンザウイルスとが融合してできたウイルスと考えられています。現在の、トリインフルエンザの蔓延の状況は、スペインかぜの蔓延の前の状況によく似ていると考えられており、世界的にも警戒が強められているのです。
 新型インフルエンザが流行すると生活はどう変わるのでしょうか?
新型インフルエンザが流行すると生活はどう変わるのでしょうか?
- 海外で発生している段階では
- 発生地への渡航は避けるよう勧告されます
- 発生地からの入国者に対する検疫が強化されます
- 国内発生の段階
- 患者さんに対しては入院が勧告されます
- 患者さんに接触した人(家族、職場の人など)の監視が必要になります
- 国内外の移動自粛が求められます
- 集会の自粛、休校、公共の場でマスク着用などが必要になります
 新型インフルエンザが流行した場合
新型インフルエンザが流行した場合
- ワクチンの開発までに6ヶ月はかかります
- 流行を最小限にとどめ、その間にワクチンを製造、順次接種することになります
- タミフルのような抗インフルエンザ薬は、普通のインフルエンザに対しては使わないようになります
- したがって、普通のインフルエンザにならないためにワクチン接種をしておくことは大切

<まとめ>
- インフルエンザの予防のために、うがい、手洗い、マスク、予防接種を
- インフルエンザにかかったかなと思ったら早めに受診を
- 新型インフルエンザの情報はしっかりチェックしましょう
<質疑応答より>
予防接種を2回うつ場合と1回の違いは?
- 基本的には、インフルエンザ予防接種は2回うつことが必要です。それは、1回目の接種で、抗体価が上がっても、しばらくすると下がってしまいます。それだけではインフルエンザシーズンをカバーすることはできません。2回目をうつと抗体価が高いまま数ヶ月持続します。つまり、ワクチンがインフルエンザシーズン中効いているということになります。しかし、65歳以上の人たちの場合は、1回でも十分効果があることが証明されているので、1回でよいのです。65歳未満の人については、基本的には2回接種をおすすめします。ただ、毎年インフルエンザワクチンを受けているとか、何度かインフルエンザにかかったことのある人は1回でも大丈夫かもしれません。その点は、あくまでも推測にすぎません。受験生などの場合は2回受けて、効果を確実にしておいた方がよいでしょう。また、2回うつというのは、1回の量を2回に分けるということではありません。
タミフルの副作用は?
- インフルエンザに罹患してタミフルを服用した人に、行動の異常などの神経症状が現れた、ということで新聞などでも大きく取り上げられました。タミフルの副作用なのか、インフルエンザの高熱のためなのか、はっきりしませんでした。その後の調査では、因果関係は証明されないということになったようですが、そのような事実はありますので、使用には慎重を期したいと思います。また、皆さんも少しでもおかしな症状があったら知らせて下さい。
新型インフルエンザがはやりだしたら、病院の待合室は危険ではないですか
- もし新型インフルエンザが流行すれば、待合室の消毒も今まで以上に必要になるでしょう。また、高血圧などの慢性疾患の一般患者さんと、インフルエンザの患者さんは時間帯や場所を分けて診なければならなくなるでしょう。診察時間などはお電話やホームページを通じてお知らせするようにしますのでご確認下さい。
今うっているインフルエンザの予防接種は、新型インフルエンザには効かないんですか?
- 今うっているインフルエンザワクチンはインフルエンザA型のH3N1型とH1N1型、そしてB型に対するものです。今、懸念されている新型インフルエンザが、トリインフルエンザからの変異型だとするとH5N1型になると予想されています。これに対しては残念ながら効果はありません。
肺炎の予防注射があると聞きましたが
- 肺炎の原因には、インフルエンザウイルス以外に、いろいろな細菌も原因となるのですが、特に肺炎球菌という菌が原因であることが多いことがわかっています。肺炎球菌に対してはワクチンがあり、肺炎を起こしやすい高齢者や肺の病気を持った人や、免疫力の弱い人には接種が勧められています。一度うっておくと5年くらい有効といわれています。ただ、今のところ2度目の接種はできませんので、接種時期は慎重に決めた方がよいでしょう。肺炎球菌ワクチンをうって、さらに、インフルエンザワクチンも毎年接種しておけば、肺炎の予防の点ではよりよいでしょう。

<参考文献>
- 加地正郎編、インフルエンザワクチン接種の実際とコツ、南山堂
- Robert B. Belshe, The origins of Pandemic Influenza- Lessons from the 1918 virus, New England Journal of Medicine, 2005年11月24日号, vol 353, p 2209- 2211
- 里村一成、北村哲久、うがい、手洗い、マスクによる予防は有効か、EBMジャーナル、2005, vol 6, p 14- 17
ホームへ
![]() インフルエンザの特徴
インフルエンザの特徴![]() インフルエンザの症状
インフルエンザの症状![]() インフルエンザの合併症
インフルエンザの合併症![]() 年齢別罹病率と死亡率
年齢別罹病率と死亡率![]()
![]() インフルエンザの予防には次のようなものが挙げられます
インフルエンザの予防には次のようなものが挙げられます![]() 予防接種
予防接種![]() 学童へのインフルエンザ予防接種の効果
学童へのインフルエンザ予防接種の効果![]() 脳炎・脳症の合併予防効果
脳炎・脳症の合併予防効果![]() ワクチンの接種時期
ワクチンの接種時期![]() ワクチンの効果をまとめますと次のようになります
ワクチンの効果をまとめますと次のようになります![]() ワクチンの副反応
ワクチンの副反応![]()
![]() 一般的予防
一般的予防![]() うがい
うがい![]() 手洗い
手洗い![]() マスク
マスク![]() 一般的予防 〜日常生活〜
一般的予防 〜日常生活〜![]()
![]() インフルエンザにかかってしまったら
インフルエンザにかかってしまったら![]() 早期診断の重要性
早期診断の重要性![]() インフルエンザの薬物治療
インフルエンザの薬物治療![]()
![]() 新型インフルエンザについて
新型インフルエンザについて![]() トリインフルエンザについて
トリインフルエンザについて![]() 数年前までの状況
数年前までの状況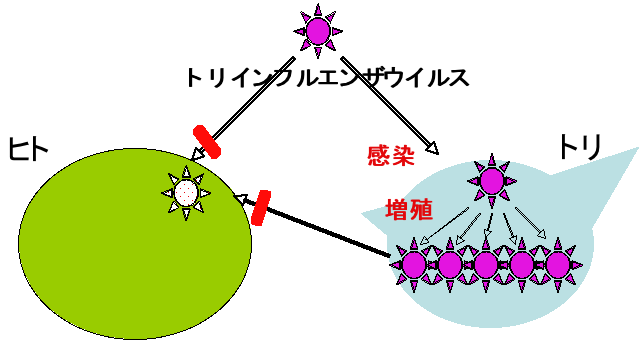
![]() 現在の状況
現在の状況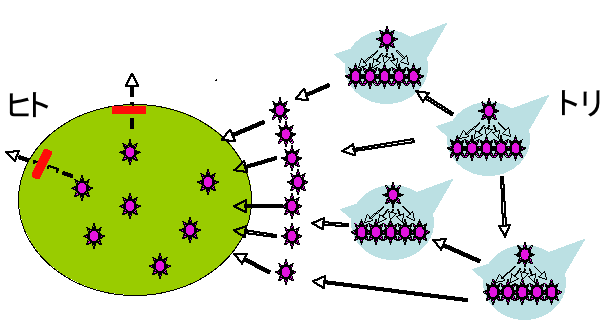
![]() これから起こると予想されている状況
これから起こると予想されている状況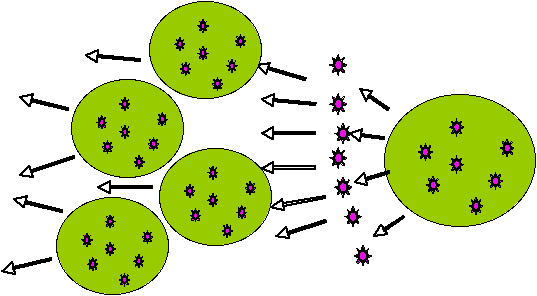
![]() 新型インフルエンザの流行の歴史
新型インフルエンザの流行の歴史![]() 新型インフルエンザが流行すると生活はどう変わるのでしょうか?
新型インフルエンザが流行すると生活はどう変わるのでしょうか?![]() 新型インフルエンザが流行した場合
新型インフルエンザが流行した場合![]()
![]()