子どもの夜型化がもたらす身体への影響
平成18年12月1日(金)ふじみ野市立福岡小学校学校保健委員会での発表より
 近年、子供の夜型化が問題となっています。夜遅くまで起きていることによって、睡眠時間が減り、日中もぼおっとした子供が増えていることが指摘されています。今回、学校保険委員会では、生徒の皆さんが睡眠について大変よく調べて発表してくれました。私からは「子どもの夜型化がもたらす身体への影響」を少し掘り下げてお話したいと思います。
近年、子供の夜型化が問題となっています。夜遅くまで起きていることによって、睡眠時間が減り、日中もぼおっとした子供が増えていることが指摘されています。今回、学校保険委員会では、生徒の皆さんが睡眠について大変よく調べて発表してくれました。私からは「子どもの夜型化がもたらす身体への影響」を少し掘り下げてお話したいと思います。
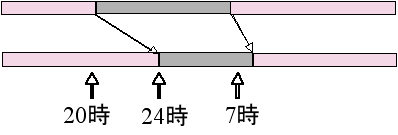
 夜型化によって変化が起こるのは大きく分けて二つあります。一つは体内時計の乱れ、もう一つはホルモンの分泌の乱れです。
夜型化によって変化が起こるのは大きく分けて二つあります。一つは体内時計の乱れ、もう一つはホルモンの分泌の乱れです。
- 体内時計
- 体内時計とは、体が日中は活動し、夜は休息するという一日のリズムが効率よく行われるようにするために、外界の実際の時間に適応するためのものと考えられています。
- 体内時計と環境との時間差
- 最もわかりやすい例は"時差ボケ"だろうと思います。飛行機で時差のある海外に到着すると、体は眠いのに昼間だったり、起きていたいのに真夜中だったりします。
- 時差ボケの症状には、...があります。
- 体内時計は25時間で動いている
- 興味深いことに、体内時計は25時間で動いているのです。ですから毎朝その時計をリセットしなければなりません。そのためには、朝日を浴びて、朝食をとることが大切です。
- それをしないと体内時計のずれが生じ、慢性的な時差ボケの状態となってしまいます。それが、夜型化によって、だるさ、イライラ、頭痛などが起きる原因となります。
- ホルモン分泌
- ホルモンとは、...
- ホルモンの一部は、一日の中で分泌量が増えたり減ったりします。それを日内変動といいますが、この日内変動が保たれていることは体のバランスを保つ上で大切で、睡眠をとることが日内変動を正常に保つために大切なのです。
- 日内変動のあるホルモン
- メラトニン
- 夜間睡眠中に分泌が増えます。睡眠を保つのに大切で、抗酸化作用があり、動脈硬化を防ぐ働きがあり、また性成熟を抑制する働きもあるといわれています。
- ステロイドホルモン
- ストレスに対するときに大切なホルモンです。朝方起床前に分泌が増えます。
- 成長ホルモン
- 夜眠りについたころに分泌が増えます。文字通り身体の成長に大切なホルモンです。寝る子は育つといわれる由縁です。
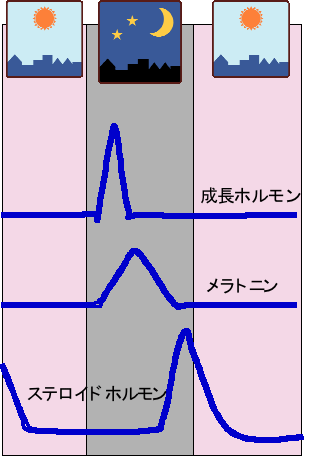
 これらのホルモンの分泌が乱れると...
これらのホルモンの分泌が乱れると...
- メラトニン
- よい睡眠が保てなくなる恐れがあります。
- 抗酸化作用が低下することにより、動脈硬化が進みやすくなること、感染に対する抵抗力が低下することがが考えられています。
- 性的成熟抑制作用が低下するため性早熟という問題が生じるのではないかと考えられています。
- ステロイドホルモン
- ストレスに対して弱くなるということが考えられます。イライラなどの原因となると考えられています。
- 成長ホルモン

 睡眠時間の減少の影響
睡眠時間の減少の影響
- 10〜14歳児を対象とした研究(米国)
- 睡眠時間11時間と5時間を比較、睡眠時間が少ないと認知能力の低下が認められたという報告があります。
- 東京都の小学生の調査
- 「朝気持ちよく起きることができない」、「夜よく眠れない」場合「学校でのイライラ」が高まるという傾向があったそうです。
- 夜更かし、朝食抜きで午前中の体温が低下
- 早寝早起きに戻すことが必要ですが、そのためにはいくつかの方法が報告されています。
- 早寝早起きにする方法
- まず早起きを
- 早寝にすることを先にするよりまず早起きにすることがよいといわれています
- 早起きをして朝の光を浴びると生体時計が同調化しやすくなる
- 朝食をとると脳の覚醒レベルが上がり、朝の目覚めがよくなる
- 昼間の活動性が高まる、運動量が増加
- 学習能力が向上、感情制御に好影響
- 就床時刻が早くなる
- 昼寝は3時までに
- 寝る前にお風呂に入る
 睡眠とストレス解消も関係があります
睡眠とストレス解消も関係があります
- 不安感、不快感、イライラ感などは大脳の神経細胞が過度に興奮して起こる。睡眠によりその興奮が静まる
- 夢をみると記憶をして残したい情報を消すのに役立つ
<まとめ>
- 家庭の事情や習い事や塾など、様々な事情はあると思いますが、睡眠をしっかりとって、すこやかな心身の成長をしてほしいと思います。
ホームへ
![]() 近年、子供の夜型化が問題となっています。夜遅くまで起きていることによって、睡眠時間が減り、日中もぼおっとした子供が増えていることが指摘されています。今回、学校保険委員会では、生徒の皆さんが睡眠について大変よく調べて発表してくれました。私からは「子どもの夜型化がもたらす身体への影響」を少し掘り下げてお話したいと思います。
近年、子供の夜型化が問題となっています。夜遅くまで起きていることによって、睡眠時間が減り、日中もぼおっとした子供が増えていることが指摘されています。今回、学校保険委員会では、生徒の皆さんが睡眠について大変よく調べて発表してくれました。私からは「子どもの夜型化がもたらす身体への影響」を少し掘り下げてお話したいと思います。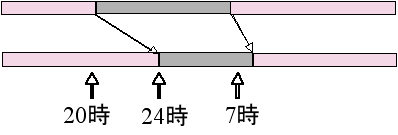
![]() 夜型化によって変化が起こるのは大きく分けて二つあります。一つは体内時計の乱れ、もう一つはホルモンの分泌の乱れです。
夜型化によって変化が起こるのは大きく分けて二つあります。一つは体内時計の乱れ、もう一つはホルモンの分泌の乱れです。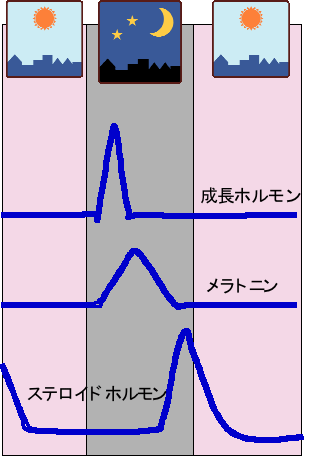
![]() これらのホルモンの分泌が乱れると...
これらのホルモンの分泌が乱れると...
![]() 睡眠時間の減少の影響
睡眠時間の減少の影響![]() 睡眠とストレス解消も関係があります
睡眠とストレス解消も関係があります