
平成17年度 ”生活習慣病予防教室 高脂血症”より
平成18年2月5日(日)、ふじみ野市立上福岡保健センターで生活習慣病セミナーが開かれ、高脂血症を担当させていただきました。ここに概要を紹介させていただきます。
|
本日の予定
|
![]() 元気でいたいーみんなの願いー
元気でいたいーみんなの願いー
今日、会場に集まった皆さんの大きな願いは、”元気でいたい”ということではないでしょうか。長生きしたい、という人もいると思いますが、生きている間は、元気で自分のことは自分でできて、好きなことを続けられる体力を持ち、みんなといろいろな話もできる能力を持ち続けたい、と考えている方が多いだろうと思います。それはつまり、いつまでも”健康でいる”ということだと思います。では、その健康を阻むものには何があるでしょう。
病気とけがが、健康を阻む大きな要因になるだろうと思います。その中でも、アンダーラインを引いた疾患は、動脈硬化が原因と考えられています。また、認知症も、多くは動脈硬化が原因とされています。脳卒中、心臓病などのいわゆる脳血管疾患は、「寝たきり」の原因の第1位でもあります。
つまり、動脈硬化は、脳血管疾患の原因であり、それは寝たきりや、生活を大きく変えてしまう原因でもあるということができます。
![]() では、動脈硬化の原因には何があるでしょうか。
では、動脈硬化の原因には何があるでしょうか。
動脈硬化の原因には、高血圧、糖尿病、高脂血症、喫煙などが重要と考えられています。
では、高脂血症(高コレステロール血症)はなぜ問題となるのでしょうか
疫学的な調査をまとめますと、総コレステロール値が高いほど、どの調査でも大体220以上の人は、動脈硬化が起こりやすいということがいえます
![]() 高脂血症の診断には、総コレステロール値、悪玉コレステロールといわれるLDLコレステロール、善玉コレステロールといわれるHDLコレステロール、そして、中性脂肪が重要です。
高脂血症の診断には、総コレステロール値、悪玉コレステロールといわれるLDLコレステロール、善玉コレステロールといわれるHDLコレステロール、そして、中性脂肪が重要です。
高脂血症の診断は次のように行います。
|
<高脂血症の診断基準>
|
このように、数値ばかりでなく、喫煙、家族歴、既往歴なども重要な要素です。
![]() ここに示しましたように、動脈硬化の危険因子は、高脂血症以外にもいくつかあるため、人によっては、それらを複数持っている人もいるわけです。実は危険因子を複数持っていると、動脈硬化を起こす危険性は非常に高くなります。たとえば、危険因子が何もない人が動脈硬化を起こす確率を1.0とすると、危険因子を1つもっている人は、5.14倍、2つ持っている人は5.76倍、そして驚くべきことは、危険因子を3〜4個持っていると35.8倍になるという点です。
ここに示しましたように、動脈硬化の危険因子は、高脂血症以外にもいくつかあるため、人によっては、それらを複数持っている人もいるわけです。実は危険因子を複数持っていると、動脈硬化を起こす危険性は非常に高くなります。たとえば、危険因子が何もない人が動脈硬化を起こす確率を1.0とすると、危険因子を1つもっている人は、5.14倍、2つ持っている人は5.76倍、そして驚くべきことは、危険因子を3〜4個持っていると35.8倍になるという点です。
すなわち、動脈硬化の危険因子は、重なると危険度はいっそう高まるといえるのです。
そこで、過去に多くの研究者たちによって、どんな人が、高血圧、高コレステロール血症、糖尿病などの危険因子を複数持つことになるかが調べられました、すると、内臓脂肪の多い人がそうなりやすい、ということがわかってきました。また、そのような人は、インスリン抵抗性が高い人ともいわれています。そのように、内臓脂肪蓄積により、体内の生化学的状態としてインスリン抵抗性が大きくなり、動脈硬化を起こしやすい状態をメタボリックシンドロームといいます。
「メタボリックシンドローム」と診断するにはどのような基準値が大切でしょう?
|
<メタボリックシンドロームの診断基準>
|
このように、内臓脂肪が多いかどうかをウエストで測ります。
ここで、今日は高脂血症の話のはずですが、ちょっと混乱される方もいらっしゃると思いますので、整理しますと。
メタボリックシンドロームと高脂血症の関係はこうなります
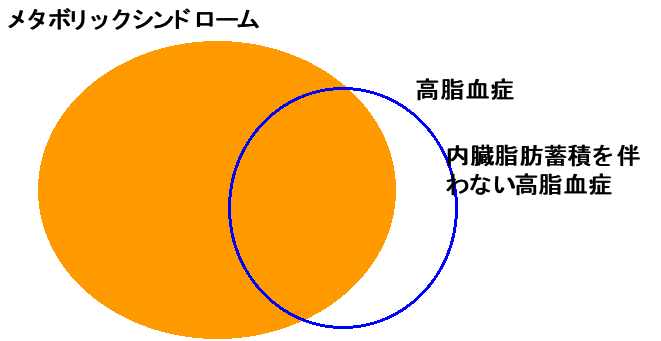
つまり、動脈硬化の原因として、高脂血症は大変重要なのですが、内臓脂肪蓄積も伴うような場合、実際には、そのような人が多いわけですが、動脈硬化の危険性はますます高くなる、ということがいえます。
メタボリックシンドロームについては、このHPでも以前に取り上げたことがあります。こちらをどうぞ。
![]() 原因はどこに?
原因はどこに?
どんな病気でも、人は誰でもその原因を知りたがります。それは、何がいけなかったのかという反省と、これからどうすればいいのかという対策のために、知りたくなるのだろうと思います。それは、現代の食生活と、運動習慣にあると考えられています。
![]() 治療
治療
さて、これからは治療の話になります。主な原因として、脂肪摂取量増加と運動量の低下が挙げられますので、まずはその反対を行うことが大切です。
したがって、運動と食事療法が大切です。
![]() 運動療法のポイント
運動療法のポイント
![]() ウォーキングの実際
ウォーキングの実際
次に大切なのは食事療法です
![]() 食事療法のポイント
食事療法のポイント
![]() 1 バランスのよい食事
1 バランスのよい食事
バランスのよい食事といってもわかりにくいと思います。バランスについて詳しく解説するとすると、糖尿病の食品交換表を使うのがもっともよい方法です。しかし、それではちょっと細かすぎますので、こんな風に考えてみてください。食品を、(1)主食(ごはん、パン、芋類)、(2)蛋白源(肉類、魚類、大豆製品)、(3)野菜類の3種類に分け、毎食必ずこの3種類をとるようにする、という具合です。簡単なようで意外と難しくもあります。毎回の食事に、必ず、この3種類の食材が含まれ、なおかつ、いろいろな食材(できれば1日30品目)をとるようにしましょう。
平成17年6月に、厚生労働省と農林水産省で策定された食事バランスガイド(こちら)も参考にして下さい。
![]() 2 適正なカロリー
2 適正なカロリー
次に適正なカロリー。これは標準体重から求めます。その人の運動量、労働量によって変わってきます。次のように計算します。
標準体重x25〜30
たとえば、身長160cmの人で、デスクワークが中心の方の場合、
だいたい、1400〜1600kCalを基準に考えればよいでしょう。
これらの食事療法は、前述した、コレステロール受容体の働きをよくし、肝臓でのコレステロールの取り込みをよくするために大切です。
![]() 3 食品中のコレステロールの制限
3 食品中のコレステロールの制限
つぎに、食品中のコレステロールを減らしましょう。食品中のコレステロールの量は、食品成分表を参考にしてください。1日のコレステロール摂取量を300mg以下にするのがよいとされています。コレステロールの多い食材の一例を示します。
| 食材 | コレステロール含有量 | 食材 | コレステロール含有量 |
|---|---|---|---|
| 卵1個(50g) | 210 mg | ししゃも3尾(60g) | 174 mg |
| 鰻蒲焼き1串(100g) | 230 mg | 鶏もも肉(皮付き100g) | 98 mg |
| たらこ1/2腹(40g) | 140 mg | 鶏レバー 50g | 185 mg |
![]() 4 飽和脂肪酸より不飽和脂肪酸
4 飽和脂肪酸より不飽和脂肪酸
脂肪のとり方にも工夫をしてください。飽和脂肪酸より不飽和脂肪酸のほうがよいといわれています。飽和脂肪酸は常温で固まる油、不飽和脂肪酸は固まらない油、と思っていただいてよいと思います。前者は動物性脂肪、つまり、ラード、バターなどが代表です。後者は、サラダオイル、オリーブオイル、魚油などが含まれます。
次に、多く食べた方がよいものは食物繊維と抗酸化物質です。
![]() 5 食物繊維を多く
5 食物繊維を多く
食物繊維は、海草類、茸類、豆類、芋類に多く含まれます。ただし、芋類、豆類はカロリーも高くなりやすいので気をつけましょう。
![]() 6 抗酸化物質を
6 抗酸化物質を
抗酸化物質は動脈硬化を防ぐ働きがあり、βカロチン、ビタミンC、ビタミンEなどが代表的です。食材としては次のようなものです。
いずれの食材も、それだけとればよいというものではありませんので、常にバランスを考えてとるようにして下さい。
![]() 薬について
薬について
![]() 高脂血症の薬物療法の効果(MEGAスタディより)
高脂血症の薬物療法の効果(MEGAスタディより)
![]() コレステロールが少ないとどのくらいリスクが少なくなるのか(J-LITより)
コレステロールが少ないとどのくらいリスクが少なくなるのか(J-LITより)
これは、もともとリスクが低いのであまり有り難みを感じませんが、高血圧、糖尿病も伴うような、いわゆるメタボリックシンドロームにあてはまるような人の場合はどうでしょう。
コレステロールが少ないとどのくらいリスクが少なくなるのか
このように、薬物療法は、ほかの危険因子も持っているような場合に特に効果が期待できます。
![]() まとめ
まとめ
|
<質疑応答より>
Q:中性脂肪が高め、γGTPが高めで脂肪肝といわれました。脂肪肝になると元には戻らないのでしょうか?生活上の注意点は何があるでしょうか?
Q:適度な飲酒量とはどのくらいですか?
Q:毎年健診で中性脂肪が200くらいあって、毎日1時間のウォーキングもしていますがなかなか下がりません。体質的なものなのでしょうか?
Q:体重は標準体重より2kg少ないのにへその周りの腹囲が85cmあります。内臓が下がっているんじゃないかと友達に言われましたが、そんなことあるんでしょうか?
Q:コレステロールと中性脂肪の理想的な値とはどのくらいですか?
Q:動脈硬化と眼底出血は関係がありますか?
Q:中性脂肪がいつも300あります。左足のしびれがあるのですが、関係はあるでしょうか?
Q:総コレステロールが290あります。薬は絶対必要なのでしょうか?左手のしびれもあり気になっています。
Q:動脈硬化の検査で血管年齢がプラス80歳といわれました。どうしたらいいのでしょうか?
Q:動脈硬化をはかることはできますか?基本健診にオプションで加えることはできますか?
Q:18歳の頃から総コレステロールが220くらいあります。中性脂肪やHDLコレステロールは正常です。家族歴はありません。食事、運動は気をつけているのですが心配です。
Q:内臓脂肪と皮下脂肪は別々に測ることはできるのでしょうか?
Q:心肥大といわれたのですが注意することはありますか?