第28回健康講座 コレステロールについて
![]() コレステロールとは
コレステロールとは
![]() 血液に油が浮いている?
血液に油が浮いている?
コレステロールは油の一種ですが、血液の中に浮いているのでしょうか?・・・いいえ、実は、血液の中で、タンパク質と結合して(これをリポ蛋白といいます)、血液の中で浮かぶことなく、血液と混じりあって全身を流れています。
![]() 近年、日本人の血液中のコレステロール値が高くなってきていることが明らかになってきました。1960年当時、男性も女性も平均血清コレステロール値は180程度でした。それが、1990年には、男性で196、女性で208程度まで高くなっているのです。その要因は、食生活にあるだろうと考えられています。日本人の食事は欧米化してきたといわれています。つまり、食材の中の穀類の割合が減り、肉類、卵類、乳製品の割合が多くなってきました。そして、栄養素で分けてみると、脂肪の占める割合が増えてきているのです。1946年当時、食事中の脂肪の割合(エネルギー比)は7.0%だったのに対し、1990年には25.3%に増えているのです。日本人のコレステロール値が高くなったのは、このように食生活が変化したことが大きいと考えられています。
近年、日本人の血液中のコレステロール値が高くなってきていることが明らかになってきました。1960年当時、男性も女性も平均血清コレステロール値は180程度でした。それが、1990年には、男性で196、女性で208程度まで高くなっているのです。その要因は、食生活にあるだろうと考えられています。日本人の食事は欧米化してきたといわれています。つまり、食材の中の穀類の割合が減り、肉類、卵類、乳製品の割合が多くなってきました。そして、栄養素で分けてみると、脂肪の占める割合が増えてきているのです。1946年当時、食事中の脂肪の割合(エネルギー比)は7.0%だったのに対し、1990年には25.3%に増えているのです。日本人のコレステロール値が高くなったのは、このように食生活が変化したことが大きいと考えられています。
![]() 年をとると高くなるのはなぜ?女性は高くなりやすいのはなぜ?
年をとると高くなるのはなぜ?女性は高くなりやすいのはなぜ?
血液中のコレステロール値は、特に女性では年齢とともに高くなる傾向があります。これは女性ホルモンの分泌と関係があると考えられています。男性は中年以降は年齢によって変化することはないようです。
![]() 血液中のコレステロールはどこからくるんだろう?
血液中のコレステロールはどこからくるんだろう?
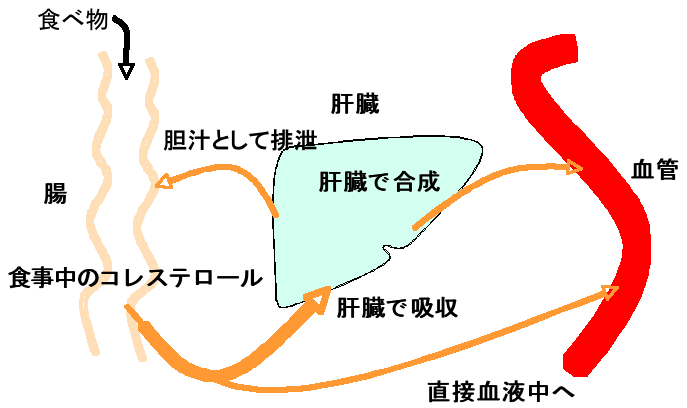
血液中のコレステロールは、食事から入ってくるもののほかに、体の中で作られるものもあります。コレステロールを作っているのは肝臓です。肝臓は体の中のコレステロールの過不足の状態に応じてコレステロールを作ります。また、血液中のコレステロールを取り込んで蓄える働きもしています。
ですから、血液中のコレステロールの値は、食事からのコレステロールの摂取量ばかりでなく、肝臓でのコレステロールの吸収量、肝臓でのコレステロールの合成量などにもよるのです。
![]() コレステロール値が高いとどうなるの?低いとどうなるの?
コレステロール値が高いとどうなるの?低いとどうなるの?
J-LITという日本人のコレステロール値の疫学調査があります。これは、約5万人の日本人について、コレステロール値と6年間の病気の発生との関係を調べたものです。それによると次のようなことがわかりました。
欧米の研究結果も全く同じで、血清コレステロール値が、240を越えると、高くなればなるほど心筋梗塞などになりやすくなる傾向がみられました。
![]() コレステロールが高いとどうして動脈硬化になるのか
コレステロールが高いとどうして動脈硬化になるのか
動脈硬化について
動脈は全身に栄養を送るパイプラインの働きをしています。下の図に示したピンク色の線が動脈です。心臓から出て、全身に栄養を送ります。
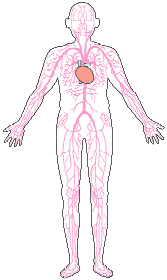
<図:全身の動脈>
この動脈がつまってしまうと、そこから先へは栄養が送られなくなり、その臓器に障害をもたらします。脳の血管に動脈硬化が起きてつまってしまうと脳梗塞に、心臓の血管がつまってしまうと心筋梗塞になってしまいます。
では、コレステロールがどのようにして動脈硬化を起こすのでしょうか。下の図に、動脈にコレステロールがたまっていく様子を示しました。動脈はパイプラインといいましたが、構造はただのパイプやチューブのような単純なものではありません。3層からなる弾力に富んだ一つの臓器といってもよいものなのです。血液中を流れる悪玉コレステロール(図中![]() )は、血液中に増えすぎると血管の内側に取り込まれて溜まっていきます(図の左上から右上への変化)。このくらいの状態なら血液の流れを妨げることもなく、特に問題はありません。しかし、さらに悪玉コレステロールが溜まると血管の内腔が狭くなり、血液の流れが悪くなってきます(図の左下)。さらに血管壁の中のコレステロールが増えると血管の内側の壁に亀裂が生じます(プラークの破綻といいます)。するとそれは血管の傷なので、修復するために血小板(図中
)は、血液中に増えすぎると血管の内側に取り込まれて溜まっていきます(図の左上から右上への変化)。このくらいの状態なら血液の流れを妨げることもなく、特に問題はありません。しかし、さらに悪玉コレステロールが溜まると血管の内腔が狭くなり、血液の流れが悪くなってきます(図の左下)。さらに血管壁の中のコレステロールが増えると血管の内側の壁に亀裂が生じます(プラークの破綻といいます)。するとそれは血管の傷なので、修復するために血小板(図中![]() )が集まってきて血栓を作ります(図の右下)。血栓というのは、血管が破れて出血したような場合は、出血を止めるために必要なのですが、このような場合は困ったことになります。急に動脈がつまってしまうことになるからです。つまり、脳や心臓の血管に生じれば、突然、脳梗塞や心筋梗塞を起こす、ということになるわけです。そして、つまったままの状態が長く続けば、麻痺や心不全などの後遺症を残してしまうのです。
)が集まってきて血栓を作ります(図の右下)。血栓というのは、血管が破れて出血したような場合は、出血を止めるために必要なのですが、このような場合は困ったことになります。急に動脈がつまってしまうことになるからです。つまり、脳や心臓の血管に生じれば、突然、脳梗塞や心筋梗塞を起こす、ということになるわけです。そして、つまったままの状態が長く続けば、麻痺や心不全などの後遺症を残してしまうのです。
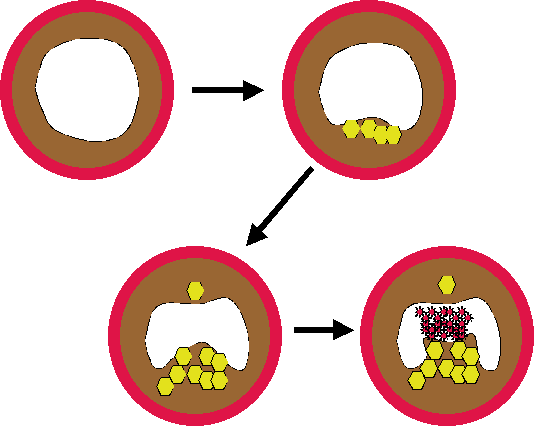
![]() 治療対象となる場合とは
治療対象となる場合とは
では、どのような場合に、高コレステロール血症として治療対象となるのでしょう。それは、数値だけで決めるのではなく、他の動脈硬化を起こしやすい要素があるかどうかなどを検討し、治療の対象かどうか考えるのがよいのです。
具体的には、やや複雑ですが、日本動脈硬化学会の基準では、以下のように考えられています。
まず、以下の危険因子をいくつ持っているか数えます
| 危険因子の数 | 総コレステロール目標値 | LDLコレステロール目標値 |
|---|---|---|
| 0 | 240 mg/dl未満 | 160 mg/dl未満 |
| 1〜2個 | 220 mg/dl未満 | 140 mg/dl未満 |
| 3個以上、または上記の5にあてはまる | 200 mg/dl未満 | 120 mg/dl未満 |
| 上記の6にあてはまる | 180 mg/dl未満 | 100 mg/dl未満 |
LDLコレステロールは次のように計算されます。
このように、危険因子をたくさん持っていること、あるいは、糖尿病を持っている、あるいは、すでに心筋梗塞、狭心症をを起こしている、といった点は重要視されます。
![]() 治療法の考え方
治療法の考え方
具体的な治療方法に話を進めましょう。治療は、食事、運動がまず大切で、それでも下がりにくければ、薬の使用を検討します。
それぞれの治療法がどこに効くのか理解すること、つまり、どうして運動が重要なのか、とか、どうして食物繊維が必要なのか、などを理解することは大切です。
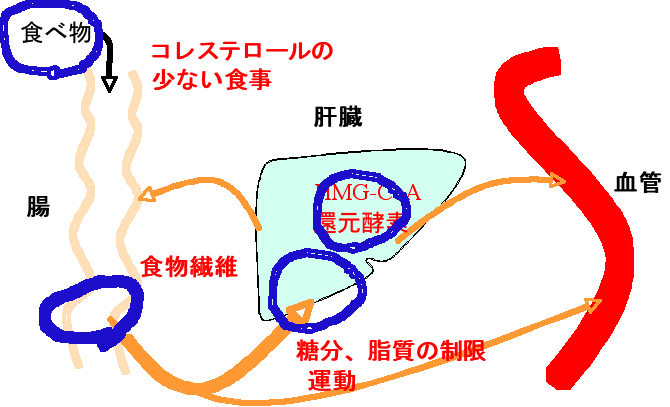
![]() 食事療法
食事療法
食事の要点は次のようなものです。
1 バランスのよい食事
バランスのよい食事といってもわかりにくいと思います。バランスについて詳しく解説するとすると、糖尿病の食品交換表を使うのがもっともよい方法です。しかし、それではちょっと細かすぎますので、こんな風に考えてみてください。食品を、(1)主食(ごはん、パン、芋類)、(2)蛋白源(肉類、魚類、大豆製品)、(3)野菜類の3種類に分け、毎食必ずこの3種類をとるようにする、という具合です。簡単なようで意外と難しくもあります。毎回の食事に、必ず、この3種類の食材が含まれ、なおかつ、いろいろな食材(できれば1日30品目)をとるようにしましょう。
2 適正なカロリー
次に適正なカロリー。これは標準体重から求めます。その人の運動量、労働量によって変わってきます。次のように計算します。
標準体重x25〜30
たとえば、身長160cmの人で、デスクワークが中心の方の場合、
だいたい、1400〜1600kCalを基準に考えればよいでしょう。
これらの食事療法は、前述した、コレステロール受容体の働きをよくし、肝臓でのコレステロールの取り込みをよくするために大切です。
3 食品中のコレステロールの制限
つぎに、食品中のコレステロールを減らしましょう。食品中のコレステロールの量は、食品成分表を参考にしてください。1日のコレステロール摂取量を300mg以下にするのがよいとされています。コレステロールの多い食材の一例を示します。
| 食材 | コレステロール含有量 | 食材 | コレステロール含有量 |
|---|---|---|---|
| 卵1個(50g) | 210 mg | ししゃも3尾(60g) | 174 mg |
| 鰻蒲焼き1串(100g) | 230 mg | 鶏もも肉(皮付き100g) | 98 mg |
| たらこ1/2腹(40g) | 140 mg | 鶏レバー 50g | 185 mg |
4 飽和脂肪酸より不飽和脂肪酸
脂肪のとり方にも工夫をしてください。飽和脂肪酸より不飽和脂肪酸のほうがよいといわれています。飽和脂肪酸は常温で固まる油、不飽和脂肪酸は固まらない油、と思っていただいてよいと思います。前者は動物性脂肪、つまり、ラード、バターなどが代表です。後者は、サラダオイル、オリーブオイル、魚油などが含まれます。
次に、多く食べた方がよいものは食物繊維と抗酸化物質です。
5 食物繊維を多く
食物繊維は、海草類、茸類、豆類、芋類に多く含まれます。ただし、芋類、豆類はカロリーも高くなりやすいので気をつけましょう。
6 抗酸化物質を
抗酸化物質は動脈硬化を防ぐ働きがあり、βカロチン、ビタミンC、ビタミンEなどが代表的です。食材としては次のようなものです。
いずれの食材も、それだけとればよいというものではありませんので、常にバランスを考えてとるようにして下さい。
(野菜食に効果があるという最新の研究結果については、このHPでもすでに紹介しました。こちらをどうぞ。)
1日にとる量として、肉類は片手に乗る程度、野菜、海草類、きのこ類は両手にいっぱい、とイメージするとよいでしょう。
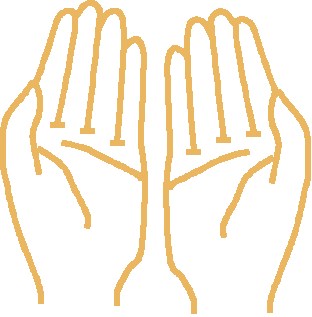
![]() 運動療法
運動療法
運動については、ジョギング、ウォーキング、水泳、水中歩行、サイクリングなどのような運動がよく、一日30分前後、週2日以上行うのがよいでしょう。
![]() 薬が必要な場合
薬が必要な場合
これらを行ってもコレステロールが下がらない場合は薬が必要となります。
薬には、肝臓でのコレステロールの合成を抑制するもの、コレステロールの吸収を抑えるものなど様々な種類がありますが、よく使われるのは、スタチン系といわれる、肝臓でのコレステロール合成を抑制するタイプのものです。これは、合成を抑制するだけでなく、肝臓でのLDLコレステロールの取り込みも促進し、この二つの作用により強力に血液中のコレステロールを下げます。薬の種類と投与量にもよりますが、スタチン系の薬の服用により、総コレステロールで大体20〜40%低下すると考えられています。
薬を飲んでいる場合はもちろん、食事療法、運動療法で治療を続けている場合も、定期的な検査も必ず受けるようにしてください。
|
<まとめ> 血液中のコレステロールが多いと、動脈硬化の原因となります。血液中のコレステロールの値は、体質と生活習慣が関係しています。
|
![]() <当日の質疑応答より>
<当日の質疑応答より>