リウマチ教室 第1回 関節リウマチの治療と日常生活
平成17年10月24日(月)、26日(水)
 今回、関節リウマチ患者さんを対象とした”リウマチ教室”を始めることに致しました。関節リウマチについては、患者さんにとって大切な情報が得にくく、一方では、患者さん達を惑わすような情報も氾濫しています。普段の外来では十分なお話もできていないと思い、このような時間を作らせていただきました。ご自身の病気について正しく理解し、治療の内容や薬の特徴について理解を深めることによって、不安も和らぎ、今後の療養にプラスとなることを期待しています。
今回、関節リウマチ患者さんを対象とした”リウマチ教室”を始めることに致しました。関節リウマチについては、患者さんにとって大切な情報が得にくく、一方では、患者さん達を惑わすような情報も氾濫しています。普段の外来では十分なお話もできていないと思い、このような時間を作らせていただきました。ご自身の病気について正しく理解し、治療の内容や薬の特徴について理解を深めることによって、不安も和らぎ、今後の療養にプラスとなることを期待しています。
 リウマチ教室の目的は、次のように考えています
リウマチ教室の目的は、次のように考えています
- 病気を正しく、よりよく理解しましょう
- ご自分の症状を理解しましょう
- 治療の必要性、目的を確認しましょう
- 薬についての理解を深めましょう
- 日常気をつけること、やったほうがよいこと、やってはいけないことを確認しましょう
- 患者さんどうしの情報も重要です
本日は第1回目として、治療と日常生活の工夫などについてお話しさせていただきます。
 本日の予定
本日の予定
- 関節リウマチの治療について
- 薬物療法
- ステロイド
- 非ステロイド消炎鎮痛剤
- 抗リウマチ薬
- 生物学的製剤
- 日常生活の工夫
- リウマチ体操
- 質疑応答
|
 関節リウマチの治療は、日常皆さんが心がけてやっていくことと、薬物療法が大切です。また、薬の副作用を少しでも少なくする工夫も大切です。
関節リウマチの治療は、日常皆さんが心がけてやっていくことと、薬物療法が大切です。また、薬の副作用を少しでも少なくする工夫も大切です。
 関節リウマチの治療
関節リウマチの治療
- 一般療法
- 薬物療法
- 非ステロイド消炎鎮痛剤、
- 抗リウマチ薬
- ステロイド、
- 生物学的製剤
- 副作用対策:胃を守るために、カルシウム、ビタミンDなど
 関節リウマチについて
関節リウマチについて
関節リウマチという病気について簡単にまとめましょう。関節リウマチは、関節の滑膜に炎症が起こり、痛みと腫れが起こり、その炎症が広がると、関節の構造も障害され、関節の働きにも影響が出てしまう病気です。関節の滑膜の炎症が起こる原因には、免疫の異常があるといわれています。したがって、関節リウマチの治療には、免疫の異常をただし、炎症を抑える薬物療法と、関節の働きの障害を少しでも減らし、回復させるための日常生活の工夫が大切です。今日はまず薬物療法から述べたいと思います。
 関節リウマチ治療薬の3本柱
関節リウマチ治療薬の3本柱
今述べた、関節リウマチの免疫異常を正し、炎症を抑えるためには大きく分けて3種類の薬があります。その3つは関節リウマチの治療の柱と考えられています。つまり、ステロイド、非ステロイド消炎鎮痛剤(いわゆる痛み止め)、この2つは主に、表面にあらわれている痛みや腫れといった炎症を抑えます。そして抗リウマチ薬は関節リウマチのもととなっている免疫異常を直します。
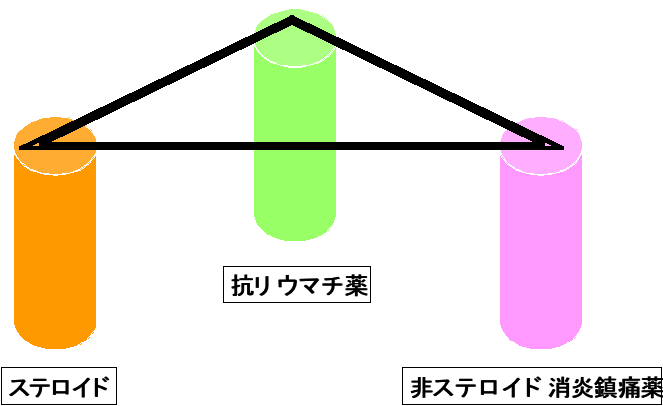
 関節リウマチの治療計画の変遷
関節リウマチの治療計画の変遷
かつては、関節リウマチの治療は、非ステロイド消炎鎮痛剤から始め、効果が不十分なら弱い抗リウマチ薬を併用し、それでも不十分なら強めの抗リウマチ薬やステロイドを使うという、ピラミッド計画といった方法がとられていました。しかし、近年、関節リウマチの治療は早期より強めの抗リウマチ薬を使った方が予後がよい、つまり、関節の障害などの後遺症も少なくてすむ、ということがわかってきました。したがって、現在は抗リウマチ薬を中心に、症状に応じてステロイドや非ステロイド消炎鎮痛薬を使うという方法になってきています。
関節リウマチ患者さんの予後が改善しているという論文をこのホームページでも紹介しました。こちらからどうぞ。
薬物療法について、順に解説していきましょう。
 ステロイドについて
ステロイドについて
- 副腎皮質ホルモン
- ステロイドは合成薬ですが、もとは、副腎という臓器から作られるホルモンです。身体の中でいろいろな働きをするホルモンです。ですから、薬として多く使っている場合に現れる副作用はホルモンとしての作用が現れるものです。
- 抗炎症作用と免疫抑制作用
- ステロイドには、炎症を抑えるだけでなく異常な免疫を抑える働きもあります。
- 1949年Hench リウマチでの効果を報告
- このときは、ベッドに寝たきりだった関節リウマチの患者さんが、ステロイドを飲んだ翌日の朝にはベッドの横で立ってダンスを踊っていたと報告され、センセーショナルなものだったそうです。しかし、その後ステロイドの副作用が問題となり、慎重な使い方がされるようになりました。
- 分類(商品名)
- プレドニン、リンデロン、メドロール、デカドロンなどがあります
- 使い方
- 関節リウマチの場合、経口投与、関節内投与などがあります。いずれも関節リウマチでは少量を使い、副作用も極力少なくするような使い方がされています。
 関節リウマチに対するステロイドの効果
関節リウマチに対するステロイドの効果
- 関節の腫れ、痛みが軽減されます
- 効果は早く現れます
- 仕事、旅行などの際に臨時薬として加えることもあります
しかし、ここで問題となるのは、副作用です。皆さんがステロイドで不安になるのはこの点が大きいと思います。副作用について理解し、その対策を講じることによって、ステロイドの副作用は少なくすることができます。
 ステロイドの副作用
ステロイドの副作用
- ステロイドの副作用は、投与量と投与期間によります
- 感染増悪、誘発
- プレドニン換算一日20mg以上の場合とくに注意が必要です
- 紫斑(あざ)、座そう様発疹(にきび)、脱毛、多毛症
- 投与期間が長くなるとこのような皮膚症状が現れる場合があります。それぞれ適切な軟膏などを使うとよいでしょう。
- 消化性潰瘍
- 大量投与のときは注意が必要です。胃薬を一緒の服用するのはそのためです。
- 糖尿病、過血糖、血栓、動脈硬化、血圧上昇
- 糖尿病、高血圧の素因のある人(家族歴がある人、既往歴がある人)では要注意ですし、すでに糖尿病や高血圧のある人では治療が必要です
- 精神変調、食欲亢進
- 不眠、食欲亢進など、やや気分がハイになるような場合もあり、ステロイドの種類を変えるなどの処置が必要となることがあります。
- 骨粗鬆症、骨折
- 少量でも長期間の服用では問題となることがわかってきました。カルシウムやビタミンDを多くとり、適切な薬物治療(骨粗鬆症の治療薬)により予防します。
- 満月様顔貌、体重増加
- 表に出やすい症状ですし、皆さんが一番気にされる副作用ではないでしょうか。食欲亢進にもなるためどうしても起こりやすい副作用です。起こることは皮下脂肪の沈着ですし、しかも、ステロイドを飲んでいると身体の中心、顔、おなか、背中に皮下脂肪が付きやすくなります。食事を工夫することで、予防しましょう。
- 白内障、緑内障(点眼薬の場合)
 ステロイドの副作用対策をまとめると次のようになります
ステロイドの副作用対策をまとめると次のようになります
- 感染症予防
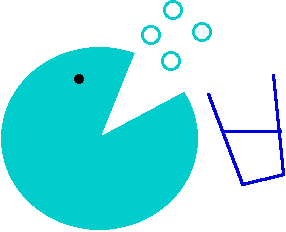
- カロリーのとりすぎに注意
- ステロイドによる肥満、糖尿病予防として。特に、脂肪分、糖分のとりすぎにならないように気をつけましょう
- カルシウムをとるようにする
- 骨粗鬆症の予防のために小魚、乳製品などをとりましょう
- カリウムをとるようにする
- ステロイド服用中はカリウムの排泄が増えますので、カリウムの多い生野菜を多くとりましょう。(ただし、高度な腎機能障害のある場合は例外です。)
- 自己判断で中止しない
- 怖いリバウンドと再燃
- 長期間ステロイドを服用していると自分の副腎はステロイドホルモンを作ることを休んでいますので、急に服用をやめてしまうと、身体に必要なステロイドホルモンさえもない状態となってしまい、ホルモン欠乏の様々な症状が現れるおそれがあります。ステロイドの減量、中止は医師の指導のもと、症状を十分確認しながら進めていきましょう。
 非ステロイド消炎鎮痛剤
非ステロイド消炎鎮痛剤
- 炎症物質であるプロスタグランジンの産生を抑制します。いわゆる痛み止めです。
- 効果
- 分類
- カルボン酸系、酢酸系、プロピオン酸系、COX2選択性などがあり、患者さんの状態、症状に応じて使い分けます
- 半減期による違い
- 一日1回、2回、3回服用などの違いは薬の半減期(薬が身体の中で残っている持続時間)によってことなります。
- 坐薬
- 胃に対する直接の副作用は少なく、効果も早く現れますので、臨時薬として併用します。
- 外用(ぬりぐすり、シップ)
- 最近は、ぬりぐすりやシップに痛み止めの成分が含まれており、大変効果があります。痛みのある関節が1,2か所のような場合や、肩だけ、あるいは膝だけどうしても痛い、というような場合、併用するとよいでしょう
- 副作用
- 胃腸障害
- 胃粘膜への直接の影響によるところもありますので空腹時の服用は避けましょう。また、胃薬が処方されている場合はきちんと飲みましょう。
- 腎障害
- 脱水になると起こりやすくなります。水分をしっかりとって定期的な検査でも確認しましょう。
- アスピリン喘息
- 喘息の患者さんの中にはアスピリンの服用で喘息が悪化する人がいます。その場合は非ステロイド消炎鎮痛剤も要注意です。
- 薬剤相互作用
- それほど多くはありませんが、飲み合わせが問題となるものもありますので、主治医によく確認しましょう。他の科にかかったときは飲んでいる薬をみていただきましょう。
 抗リウマチ薬
抗リウマチ薬
関節リウマチの治療に使われる抗リウマチ薬(免疫抑制剤を含む)には次のようなものがあります。
- 注射金剤(シオゾール)
- オーラノフィン(リドーラ)
- Dペニシラミン(メタルカプターゼ)
- ブシラミン(リマチル)
- ロベンザリット(カルフェニール)
- アクタリット(オークル、モーバー)
- スルファサラジン(サラゾピリン、アザルフィジンEN)
- ミゾリビン(ブレディニン)
- メソトレキサート(リウマトレックス)
- レフルノミド(アラバ)
- タクロリムス(プログラフ)
現在は、ブシラミン、スルファサラジン、メソトレキサートが主流となっており、それでも効果が得られないときには、レフルノミド、タクロリムスなどの投与が検討される、といったケースが多いかと思います。その他の抗リウマチ薬も、他の抗リウマチ薬と併用することにより効果が得られること多くあります。
今回は、個々の抗リウマチ薬の解説は省略しますが、抗リウマチ薬全般に共通した事柄を解説します。
 抗リウマチ薬の特徴
抗リウマチ薬の特徴
- 患者さんによって効果が違う
- 同じ抗リウマチ薬でも効く人と効かない人があって、投与前にその予測をすることはできません。そこがこの薬の欠点ではあります。
- 効果が出るのに2〜3ヶ月かかる
- 効果が出ると、痛み止めやステロイドなどが減らせることも多い
- 病状が落ち着いて、抗リウマチ薬だけ服用する人もいます
- 副作用の頻度が比較的高い
- 皮膚のかゆみなどの軽い副作用から、蛋白尿、間質性肺炎などの副作用がありえます。もちろん副作用の起こらない人の方が多いのですが、薬をやめてもすぐに回復に時間がかかる場合もあるので、定期的な診察や検査の中で副作用が出ていないか確認することも大事です。副作用が出たことのある薬は再び使うと同じ副作用が起こる可能性は高いので、今までどんな薬を使ったか、副作用があったかどうかは重要な情報です。
- 効果があっても長年使っていると効果が弱くなってくることがある
- 効果があっても時間がたつと薬の変更が必要となることがあります。
 つぎに、近年の関節リウマチの治療を大きく変えることになると期待されている、新しい薬を紹介します。それは、生物学的製剤といわれるものです。そのような変わった名前が付いているのは、今までの薬が化学的に合成した化合薬であるのに対して、生物学的製剤はヒトが持っている抗体あるいは、受容体といわれる構造を遺伝子工学の力で作ったものであるからです。
つぎに、近年の関節リウマチの治療を大きく変えることになると期待されている、新しい薬を紹介します。それは、生物学的製剤といわれるものです。そのような変わった名前が付いているのは、今までの薬が化学的に合成した化合薬であるのに対して、生物学的製剤はヒトが持っている抗体あるいは、受容体といわれる構造を遺伝子工学の力で作ったものであるからです。
関節リウマチの根本原因はまだ解明されていませんが、かなり原因に近いところで起きていることはわかってきました。その一つが、関節リウマチの炎症にはTNF-αという物質の影響が大きいということです。前述した抗リウマチ薬も、多かれ少なかれ、TNF-αという物質の産生を抑えるという働きを持っています。つまり、関節リウマチの治療においては、そのTNF-αを抑える、ということがポイントとなるのです。そこで開発された薬が、TNF-αに対する抗体や、TNF-αの受容体を薬とした、インフリキシマブ(商品名レミケード)、エタネルセプト(商品名エンブレル)といった薬なのです。
 生物学的製剤の特徴
生物学的製剤の特徴
- 関節リウマチの炎症を起こす物質の中でもっとも影響の大きいTNF-αという物質を直接抑制する
- 抗体であるので、他への影響はほとんどない
- ”痛み止めが胃や腎臓にも影響する”というようなことはない
- 抗体であるので、体にとっては”異種たんぱく質”であるので、アレルギーの原因となりうる
- TNF-αを抑制することによる副作用も問題
- 感染症、とくに結核
- TNF-αは、もともと感染症のときに身体を守るために働く物質でもあるのです。その働きを抑えてしまうことで感染症に対して抵抗力が弱くなったり、感染症を起こしたときの症状が軽く、症状が起きたときは思いの外重症であったりすることがあります。
そのような製剤ですが、関節リウマチに対する効果にはすばらしいものがあります。
 生物学的製剤の効果
生物学的製剤の効果
- 痛みを抑える効果が強く、効果は早く見られる
- 炎症所見は速やかに低下
- レントゲン上、関節の変化の進行が遅く、回復する場合もある
- 早期に使えば、寛解状態に持っていける可能性もある
しかし、まだまだ問題点もあります。
 生物学的製剤の問題点
生物学的製剤の問題点
- 注射であること
- 点滴(2ヶ月毎、2〜3時間)、皮下注射(週2回)(平成17年10月現在)
- 副作用:アレルギー、投与時反応、感染症
- 薬価が高いこと
- いつまで続けるのか、という点が未解決
- 長期間使った場合の体への影響が未知
- 日本より早くから使われている欧米でも、まだ10年ほどの歴史しかありませんので、長期間の投与による副作用などはまだわかっていないのが現状です
現在の関節リウマチの薬物治療は、早期から強めの抗リウマチ薬を使って炎症を抑え、それでも十分効果が得られなければ生物学的製剤の使用を考える、という方法がとられるようになり、関節リウマチの予後も大きく変わってきました。(関節リウマチの予後の改善に関する論文についてはこちらもご覧下さい)
以上、関節リウマチの薬物療法について解説しました。つぎに、日常生活での様々な工夫について紹介しましょう。この点はもしかすると患者さんの方がいろいろな知恵を持っていらっしゃるかもしれません。
関節リウマチの一般療法について
 高血圧、糖尿病などでは、食事療法や運動療法など、患者さん自身が取り組むべきものがたくさんあり、また、それらの効果もはっきりしています。それらの疾患では、患者さんの生活習慣に原因がある場合も多く、生活習慣改善の必要性がわかりやすいと思います。しかし、関節リウマチでは、原因は患者さんの生活習慣ではありません。その点が患者さんが、治療に対して受け身になってしまい、自分は何をやってよいかわからず悩んでしまう要因ともなっているのではないかと思います。治療効果を上げ、関節の機能を維持していく上ではこれから紹介するような日常生活の工夫がとても大切になってきます。
高血圧、糖尿病などでは、食事療法や運動療法など、患者さん自身が取り組むべきものがたくさんあり、また、それらの効果もはっきりしています。それらの疾患では、患者さんの生活習慣に原因がある場合も多く、生活習慣改善の必要性がわかりやすいと思います。しかし、関節リウマチでは、原因は患者さんの生活習慣ではありません。その点が患者さんが、治療に対して受け身になってしまい、自分は何をやってよいかわからず悩んでしまう要因ともなっているのではないかと思います。治療効果を上げ、関節の機能を維持していく上ではこれから紹介するような日常生活の工夫がとても大切になってきます。
ここでは次のようなことを解説します。
日常生活と一般療法
- 薬の飲み方
- 食事
- 運動と安静
- 関節の保護
- リウマチ体操
- 通院の際の工夫
 薬の飲み方、使い方について
薬の飲み方、使い方について
- 多くの薬は食後に服用することになっています。特に非ステロイド消炎鎮痛剤は空腹時に服用すると胃によくありません。必ず食後に服用し、どうしても無理な場合は、牛乳で飲んでも構いません。
- 逆に、空腹時に服用しなければいけない薬もあります。骨粗鬆症の薬がそうです。その手の薬を服用している患者さんも多いと思います。
- 座薬は、明け方の痛みやこわばりが強い場合に、寝る前に使用すると効果がある場合があります。
- 座薬は冷蔵庫で保管しますが、冷蔵庫から出してすぐ使うと、直腸の粘膜を傷つけることにもなりますし、薬としての吸収も低下します。30分くらいは室温に置いてから使いましょう。暖めすぎると溶けるので注意しましょう。
- また、座薬を入れたときは、おならに気をつけましょう。夜挿入した場合でも、翌朝くらいまでは座薬の基材である油が直腸内に残っています。おならをするとその油がでてしまうことがありますのでご注意を。
- 薬の飲み方、使い方はよく確認しましょう。
 食事療法のポイント
食事療法のポイント
- カロリ-

- 1400〜2000カロリ-
- 炎症の強い時期(発熱、全身倦怠、食欲不振などの症状の強い時期)は多めにカロリ-をとるようにする
- 高カルシウム
- 牛乳、乳製品、小魚、しらすぼし、大豆、卵黄、緑黄色野
- ビタミンDはカルシウムの吸収を助ける
- 乾し椎茸、マグロの刺身、いわし、かつお、レバ−、卵黄、さつま揚げ
- 高カリウム
- ステロイドを服用していると排泄が高まるので
- 生野菜、大豆製品、じゃがいも、かぼちゃ、果物、海藻
- 脂質
- 魚の脂はリウマチ、膠原病にはよいと考えられています
- アレルギーの関与がある場合は、その食材は控える
 日常生活の工夫
日常生活の工夫
 安静を上手にとるようにしましょう
安静を上手にとるようにしましょう
- ベッドは硬いものを使いましょう
- 頭を床におしつけ、背筋が伸びた状態を5分間続け、その後は楽な姿勢で休む
- 腰が沈んでしまうような柔らかいベッドで休むと腰によくないためです
- 椅子で休むときは両足底が床につき、背筋がまっすぐに伸びる椅子を使う
- 柔らかいソファ−はよくない
- これも同じく、腰が沈んでしまうと腰によくないだけでなく、首にもよくないことや、起きるとき、膝への負担が大きいことなどが理由です
 リウマチ体操
リウマチ体操
具体的な方法については、リウマチ情報センターのホームページの、リウマチ体操のページや、参考文献(1)などを参考にしてください。
- 関節、筋肉を強くするために行います
- 普通、一日2〜3回、特に温浴のあとで行うと効果的です
- 運動のあと、痛みが増しても、1〜2時間で元に戻るようなら続けても構いません
- ご自分の症状を調べながら適度に行うようにして下さい。
 大腿四頭筋の運動
大腿四頭筋の運動
特に、膝が痛い場合、大腿四頭筋という太ももの筋肉を弱らせないようにしておくことが大切です。
 外反母趾対策
外反母趾対策
外反母趾の予防と治療には、足の体操や靴の工夫が大切です。
- 靴の選択
- 幅の広い、踵の低めのもの
- はな緒のあるようなもの
- ア−チのあるもの。パットを応用。(装具屋さんで作った靴は保険で助成されます)
- 足の底は、「土踏まず」を中心に前後にも左右にも中央がふくらんだ構造をしています(アーチ構造といいます)。この構造を保つことが外反母趾の予防に重要なのです。
- 足の体操
- このホームページの健康ひとくちメモの中でも紹介した体操です。こちらもご参考になってください。
- 外反母趾予防用装具を使用
- 町のドラッグストアなどでも売っています。いろいろ試してみるとよいでしょう。
 日常生活動作の工夫、特に手に関して
日常生活動作の工夫、特に手に関して
- コ−ヒ−カップは両手で、一方は底から支えるように
- 急須は手のひらにかけ、もう一方で蓋を押さえる
- 鍋の取っ手は指で持たず、手袋を使って手全体で持つように
- 鞄は腕にかけるかショルダ−に
- ぞうきんがけは親指側へ、小指側にかけると手首に負担がかかる
- ぞうきん絞りは水道の蛇口をつかって両手で
 リウマチの関節保護
リウマチの関節保護
- 十分な休養、昼寝を含む。入浴、温泉はよい。
- 努力しすぎない
- 同じ姿勢を長く続けない
- 以下の場合は運動量過多。翌日は少なめに
- 運動中、作業中に痛みがでる、
- 運動中、作業中に痛みが増す、
- 運動後、作業後に痛みが1時間以上続く
- 変形を増長させるような方法、肢位をとらない
- 毎日適切な運動
- 1日2回最大可動域まで動かす
- 自助具の使用
 痛みに対する対処
痛みに対する対処
- よくある質問
- 温めた方がいいいのですか?冷やした方がいいのですか?
- 動かした方がいいのですか?動かさない方がいいのですか?
- 炎症の強い時期(腫れ、熱感がある)は動かさない。痛みに対して冷やすのはよい。温めない方がよい。
- 炎症が軽くなってきたら温、冷どちらでもよい。他動的に動かす。痛みが残るようならやりすぎ。
- 炎症がなくなったら(痛みは軽くなっている)自動的に動かす。リウマチ体操を積極的に行う。
 まとめ
まとめ
- 関節リウマチという病気について、治療について、理解を深めましょう
- 薬の特徴、副作用対策について理解しましょう
- 日常生活の中でのちょっとしたことが治療につながります
- 疑問な点、不安な点は遠慮なく聞いてください
<質疑応答>
Q:ステロイドを長期間続けることについての不安なのですが
A確かに薬は少ないに越したことはありませんが、ステロイドによって痛みや腫れが軽減され、日常生活も楽になります。一方で副作用も気になります。副作用対策をすることにより、副作用はできるだけ減らすことができます。副作用をできるだけ減らし、生活の中でステロイドの効果を最大限に生かすように考え、副作用対策も続けていくという考え方でいかがでしょうか。ステロイドの量は、病状を確認しながら極力減らすようにしていきたいと思います。
Q:一度飲み忘れただけで起き上がれないくらい具合が悪くなった。また飲んだら翌日には元に戻った、そんなに効くことがかえって不安
A:確かにステロイドの効果は劇的なことがあります。特に、投与量が多い場合や、抗リウマチ薬がまだ効いていなくて、ステロイドで症状を抑えているようなときにはそのようなことが起こり得ます。抗リウマチ薬が効いてステロイドが減るまでは特に、飲み忘れに気をつけてください。
Q:子供や孫への遺伝は?
A:リウマチは遺伝性の疾患ではありません。確かに、親、兄弟などの親戚にもリウマチの患者さんがいらっしゃる場合は多いです。しかし、たとえば、一卵性双生児の場合で、一方の方がリウマチでも、もう一人も必ずリウマチになるわけではありません。つまり、遺伝子が全く同じ一卵性双生児でも必ず同じ病気になるわけではありません。関節リウマチの発病は遺伝だけで決まるわけではありません。ですからあまり心配しすぎる必要はありません。ただし、もし、こわばりや関節痛があるようでしたら早めに受診して下さい。
Q:リウマチは左右対称に起こるといわれているが、今は片方だけですが、いずれ反対にも起こるのでしょうか
A:リウマチの関節炎は左右対称に起こるといいますが、必ずそうなるわけではありませんので、あまり心配することはありませんが、もし反対にも症状が現れた場合は薬が十分効いていないということですから、治療の検討が必要であることを意味しています。
Q:関節リウマチは難病の認定などは受けられるのでしょうか
A厚生労働省の特定疾患、いわゆる難病認定が受けられるのは、関節リウマチの中でも、血管炎を併発した、悪性関節リウマチというタイプの関節リウマチの場合だけです。また、関節リウマチの患者さんで、障害の程度が重ければ身体障害者手帳の交付を受けることはできます。
Q:リウマチ体操は一日に何回くらいやったらいいのですか
A少なくとも風呂上がりの筋肉のほぐれているときには一回行って下さい。それ以外に、日中もう一度行うとよいでしょう。手に関しては、洗面器などにお湯を張って、そこで手を暖めてから行うとよいでしょう。一回に、各運動を、10〜20回を目安に、痛みが増さない、痛みが残らない、というのを目安に行って下さい。
Q:プールで歩くのがいいと聞きますが、冷えすぎてよくないということはないですか
A:市内の温水プールであればまず冷えすぎてよくない、という心配はありません。膝、股関節に炎症がある場合、プールがお近くにあるようでしたら是非行って下さい。
Q:リウマトレックスを飲み忘れた場合はどうしたらよいでしょうか
A:たとえば、毎週木曜日の朝、晩に服用しているとします。木曜日の朝のみ忘れたのを木曜日の昼に思い出したとします。その場合は、木曜日の晩と金曜日の朝に服用して下さい。リウマトレックスは十二時間あけて服用することが重要です。また、週に一回ですが、その方法ならのみ忘れがあっても半日のズレですみます。次の週はまた木曜日の朝に服用して下さい
<参考文献>
- 改訂新版、膠原病を克服する 療養のための最新医学情報、橋本博史著、保健同人社 (関節リウマチだけでなく膠原病全般について詳しく書かれています)
- 膠原病・リウマチは治る、竹内勤著、文春新書(関節リウマチの原因、最新治療、生物学的製剤などについて詳しく書かれています)
- リウマチ情報センターのホームページ(関節リウマチについて様々な知識の情報源となります)
- 慢性関節リウマチ患者への日常生活指導、安藤聡一郎、リウマチ科、2002年2月号、632-640(私が書いた総説です、医師向けです)
![]() 今回、関節リウマチ患者さんを対象とした”リウマチ教室”を始めることに致しました。関節リウマチについては、患者さんにとって大切な情報が得にくく、一方では、患者さん達を惑わすような情報も氾濫しています。普段の外来では十分なお話もできていないと思い、このような時間を作らせていただきました。ご自身の病気について正しく理解し、治療の内容や薬の特徴について理解を深めることによって、不安も和らぎ、今後の療養にプラスとなることを期待しています。
今回、関節リウマチ患者さんを対象とした”リウマチ教室”を始めることに致しました。関節リウマチについては、患者さんにとって大切な情報が得にくく、一方では、患者さん達を惑わすような情報も氾濫しています。普段の外来では十分なお話もできていないと思い、このような時間を作らせていただきました。ご自身の病気について正しく理解し、治療の内容や薬の特徴について理解を深めることによって、不安も和らぎ、今後の療養にプラスとなることを期待しています。![]() リウマチ教室の目的は、次のように考えています
リウマチ教室の目的は、次のように考えています![]() 本日の予定
本日の予定![]() 関節リウマチの治療は、日常皆さんが心がけてやっていくことと、薬物療法が大切です。また、薬の副作用を少しでも少なくする工夫も大切です。
関節リウマチの治療は、日常皆さんが心がけてやっていくことと、薬物療法が大切です。また、薬の副作用を少しでも少なくする工夫も大切です。![]() 関節リウマチの治療
関節リウマチの治療![]() 関節リウマチについて
関節リウマチについて![]() 関節リウマチ治療薬の3本柱
関節リウマチ治療薬の3本柱
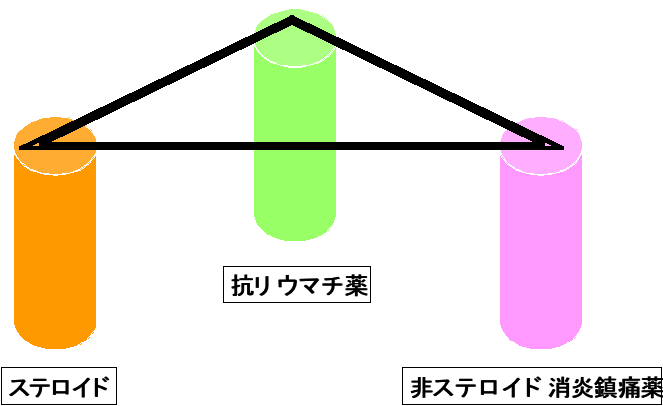
![]() 関節リウマチの治療計画の変遷
関節リウマチの治療計画の変遷![]() ステロイドについて
ステロイドについて![]() 関節リウマチに対するステロイドの効果
関節リウマチに対するステロイドの効果![]() ステロイドの副作用
ステロイドの副作用![]() ステロイドの副作用対策をまとめると次のようになります
ステロイドの副作用対策をまとめると次のようになります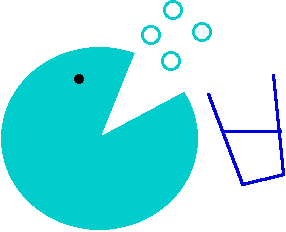
![]() 非ステロイド消炎鎮痛剤
非ステロイド消炎鎮痛剤![]() 抗リウマチ薬
抗リウマチ薬![]() 抗リウマチ薬の特徴
抗リウマチ薬の特徴![]() つぎに、近年の関節リウマチの治療を大きく変えることになると期待されている、新しい薬を紹介します。それは、生物学的製剤といわれるものです。そのような変わった名前が付いているのは、今までの薬が化学的に合成した化合薬であるのに対して、生物学的製剤はヒトが持っている抗体あるいは、受容体といわれる構造を遺伝子工学の力で作ったものであるからです。
つぎに、近年の関節リウマチの治療を大きく変えることになると期待されている、新しい薬を紹介します。それは、生物学的製剤といわれるものです。そのような変わった名前が付いているのは、今までの薬が化学的に合成した化合薬であるのに対して、生物学的製剤はヒトが持っている抗体あるいは、受容体といわれる構造を遺伝子工学の力で作ったものであるからです。![]() 生物学的製剤の特徴
生物学的製剤の特徴![]() 生物学的製剤の効果
生物学的製剤の効果![]() 生物学的製剤の問題点
生物学的製剤の問題点![]() 高血圧、糖尿病などでは、食事療法や運動療法など、患者さん自身が取り組むべきものがたくさんあり、また、それらの効果もはっきりしています。それらの疾患では、患者さんの生活習慣に原因がある場合も多く、生活習慣改善の必要性がわかりやすいと思います。しかし、関節リウマチでは、原因は患者さんの生活習慣ではありません。その点が患者さんが、治療に対して受け身になってしまい、自分は何をやってよいかわからず悩んでしまう要因ともなっているのではないかと思います。治療効果を上げ、関節の機能を維持していく上ではこれから紹介するような日常生活の工夫がとても大切になってきます。
高血圧、糖尿病などでは、食事療法や運動療法など、患者さん自身が取り組むべきものがたくさんあり、また、それらの効果もはっきりしています。それらの疾患では、患者さんの生活習慣に原因がある場合も多く、生活習慣改善の必要性がわかりやすいと思います。しかし、関節リウマチでは、原因は患者さんの生活習慣ではありません。その点が患者さんが、治療に対して受け身になってしまい、自分は何をやってよいかわからず悩んでしまう要因ともなっているのではないかと思います。治療効果を上げ、関節の機能を維持していく上ではこれから紹介するような日常生活の工夫がとても大切になってきます。![]() 薬の飲み方、使い方について
薬の飲み方、使い方について![]() 食事療法のポイント
食事療法のポイント
![]() 日常生活の工夫
日常生活の工夫![]() 安静を上手にとるようにしましょう
安静を上手にとるようにしましょう![]() リウマチ体操
リウマチ体操![]() 大腿四頭筋の運動
大腿四頭筋の運動![]() 外反母趾対策
外反母趾対策![]() 日常生活動作の工夫、特に手に関して
日常生活動作の工夫、特に手に関して![]() リウマチの関節保護
リウマチの関節保護![]() 痛みに対する対処
痛みに対する対処![]()
![]() まとめ
まとめ![]()